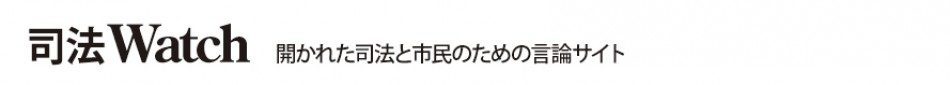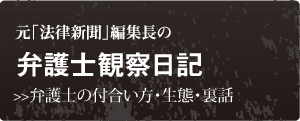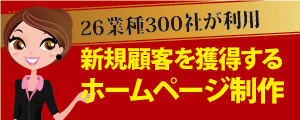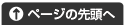司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
〈バイデンとトランプの恩赦合戦〉
アメリカでは、バイデンとトランプの間で、恩赦合戦が行われた。
トランプは、大統領就任後、早速、2021年1月6日議事堂襲撃事件(トランプが前年の大統領選挙でバイデンに敗れたのは選挙に不正があった、「選挙が盗まれた」と言って、民衆に議会での選挙結果の最終確定を妨害するように煽ったことにより生じた襲撃事件)で有罪が確定し服役していた1500名以上に対する免責・減軽を実施した。
これに先立ち、バイデンは、自分の息子や親族と、暴力犯を除く薬物事犯等の囚人1500名以上に恩赦を与え、議事堂襲撃事件下院調査委員会のメンバー等への恩赦を発表した。さらに、連邦死刑囚40人中37人を仮釈放なしの終身刑に減刑した。
親族や下院委員会メンバーへの恩赦は、トランプが、大統領就任後に司法省を使って、自己に敵対的だった者に復讐すると公言していたために、これを事前に防ぐためになされたものである。すなわち、有罪判決どころか捜査も行われていない時点での防衛的・包括的恩赦ということになる。連邦憲法は大統領の恩赦権限を規定するが、その要件や範囲をほとんど規定していないために、このような恩赦が可能なのかは議論がありうるが、過去には、カーター大統領がベトナム戦争後に、徴兵忌避者を、その対象を個別に特定せずに、恩赦とした例がある。
死刑囚に対する恩赦は、議員時代は厳罰主義者だったバイデンが、大統領として死刑廃止論を唱えていたところ、第1次トランプ政権が12人もの死刑執行をした経緯があり、第2次トランプ政権がさらに大量執行をする可能性があることを予期して、ヘイト・クライム犯とテロ実行犯の3人を除いて減刑したのである。これは、連邦における史上最大の死刑減刑である。なお、各州には合計で2100人の死刑囚がいるが、大統領の権限は州の死刑制度に及ばないので、これらは今回の恩赦の対象にはならなかった。もっとも、各州の憲法や法律は知事の恩赦権を認めている。実際、2003年、イリノイ州の知事が、死刑囚の雪冤が続き、刑事司法制度に疑いの目を向け、164人の死刑囚の減刑を実施した。同州はその後、死刑制度そのものを廃止した。
〈死刑減刑か執行停止を検討すべき日本の現状〉
日本にも恩赦制度はある。明治憲法では、主権者である天皇が臣民に恩寵により赦しを与えるものとされた。戦後、新憲法になって、天皇は国民統合の象徴となり、国民が主権者となった。天皇は国民に恩寵を与える立場にない。従って、恩赦制度はあるものの、これを決定するのは内閣であり、天皇はこれを「認証」することになった。「認証」と言っても、天皇には内閣の決定を拒否することはできず、「認証」という形式行為をするだけである。
そうとすれば、「恩赦」という表現は誤解を招く。アメリカの事情を紹介した際、「恩赦」と表現したが、英語ではpardon又はexecutive clemencyである。直訳すれば、赦し又は行政的温情と言えよう。わが現行憲法でも「恩赦」と規定するので、本稿では恩赦と言うが、本当は、温情的行政措置とでもいうのが実態に即していると言えよう。
さて、日本で減刑された死刑囚は、1975年の福岡事件を最後に存在しない。それ以前の戦後における死刑恩赦は、未成年者に対するもの、あるいはサンフランシスコ講和条約批准恩赦がほとんどである。
先ほど、イリノイ州の死刑囚雪冤続出を契機になされた恩赦を紹介したが、日本では、1980年代に4つの死刑囚再審無罪事案(松山、島田、免田、財田川各事件)で冤罪が立て続けに判明したにも関わらず、これを理由に、他の死刑囚の恩赦や執行停止がなされたことはない。無辜の者が誤判による死刑になるなどということは、あってはならないことである。日本政府は、確定死刑囚中に無辜がいるかもしれないと心配にならないのであろうか。現に、冤罪が疑われる死刑事例が、名張事件(獄中死)、福岡事件(執行)、帝銀事件(獄中死)、飯塚事件(執行)等、いくつも存在するのにである。
実際には、執行を躊躇するどころか、真相隠しのために執行を速めたのではないかと疑われる例さえある。飯塚事件である。
この事件は、二人の少女が殺され、事件から約2年半後、Aさんが逮捕され、警察庁科学警察研究所による導入後間もないDNA鑑定が最有力の証拠となって、有罪となり死刑が確定した、というものである。
ところで、幼女殺人事件で、上記と同様の方法で、かつ鑑定技官も同一のDNA鑑定による結果が証拠となって有罪となった別の事件がある。足利事件である。この事件は、再審審理で東京高等裁判所が改めてDNA鑑定をすることを決定し、結局、科警研のDNA鑑定の誤りが明らかとなり、再審で無罪となった。
ところが、この東京高裁決定のわずか2か月前、Aさんは死刑執行されてしまった。法務省は、足利事件で科警研のDNA鑑定の信用性が問題になっていたことを知っていた。また、飯塚事件弁護団が再審請求を準備中であることも知っていた。そして、飯塚事件の死刑確定からわずか2年しか経過していなかった。通常、執行は死刑確定から5年以上は経過してなされる。オウム真理教信者13名の死刑執行は確定後6年以上経過している。
少しでも、誤判による死刑を回避しようという気があれば、以上のような状況下、このような短兵急な執行は思いもつかないはずである。法務省は、新規導入したばかりのDNA鑑定技法を守りたかったためか、真相を明かす暇も与えず、Aさんを、そして事件そのものを、あの世に送ってしまおうとしたというべきでろう。
2024年、袴田事件の再審無罪が確定した。政府は、この機会に、一度立ち止まって、誤判の原因を徹底的に追及するとともに、死刑制度の存否・あり方を真剣に検討し、それらの結論が出るまでは、100人以上存在する死刑囚の減刑をするか、少なくとも、死刑の執行を停止するべきであろう。
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第6回 アメリカの司法積極主義と司法消極主義――その1
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第14回 学生ローンの日米比較
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第25回 アメリカの陪審裁判と日本の裁判員裁判
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第30回 トランプ大統領は王様か
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第24回 手続的公正と実体的真実
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第31回 陪審裁判・裁判員裁判の危うさ
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第7回 アメリカの司法積極主義と司法消極主義――その2
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第20回 死刑の誤判
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第23回 高い有罪率と検察の力
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第11回 二重の危険の日米比較――その2
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第17回 「合法集会蹴散らしの罪」
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第22回 死刑と差別
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第15回 弁護士の守秘義務
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第4回 国と自治体の関係
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第28回 無期懲役囚の逮捕
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第29回 恩赦合戦と死刑減刑
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第2回 アーカンソー州の死刑執行とその理由
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第27回 人質司法(保釈制度再論)
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第12回 没収と罪刑の均衡
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第18回 トランプ大統領の恩赦
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第10回 二重の危険の日米比較――その1
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第5回 連邦議会の立法権限の限界
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第16回 「ポリス・パワー」
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第26回 米高等教育における人種格差と最高裁判決
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第3回 アメリカ連邦憲法修正条項は州を拘束するか
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第19回 多数決か全員一致か
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第21回 二重の危険の日米比較――その3
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第9回 東京医大入試不正操作とハーバード大学入学選考差別――その2
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第1回 アメリカの保釈金制度と日米の若干の比較
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第8回 東京医大入試不正操作とハーバード大学入学選考差別――その1
- 「樋口和彦の米国司法レポート」 第13回 アメリカ大量投獄時代の意味するもの