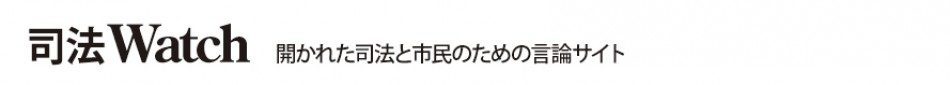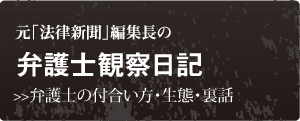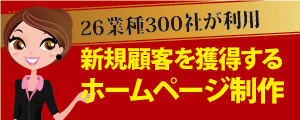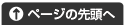司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
政治家をはじめ、政策推進者がよく口にする「国民の理解が得られない」という言葉には、気が付けば、とても欺瞞的なイメージがついてしまったように見えて仕方がない。本来、国民の理解を重視し、国民の意思を忖度していると取れていいはずの、国民が歓迎していい、この言葉が、必ずしもそう受け取れないとすれば、それは取りも直さず、使う側の心底がすっかり見えてしまったから、というほかない。
一つは、この言葉が極めてご都合主義的に使われてきたことだ。何かできない、あるいは何かしないわけにはいかない弁明として、「国民の理解」が、あたかも民主主義国家における「錦旗」のごとく、登場する。反対論を黙らせ、反論を許さない効果に期待するものであるのは、はっきりしている。
しかも、不思議なくらい、その中身が争われることがあまりない。本当に「国民の理解が得られない」のか、「得られない」とすれば、それはいかなる条件のもとで、その条件を満たすことは本当にできないのか、など。まさに「錦旗」のごとく、これを持ち出されては黙るしかない、というように。
それだけに、これを使う政府などは、明らかにこの言葉を、実に都合よく、推進政策を選んで繰り出している観がある。最近、ネット上では、政府が所得制限撤廃や減税といった議論を交わす論法の中に、これを繰り出しているという批判がみられる。そもそも減税が政府の言う通り財源の問題や将来へのツケ回しとなるといったことに「国民が反発する」と決めつけ、減税しないことに「理解が得られない」とはどうしても考えようとはしない、のである。
そして、もう一つは、こうしたことを最上段で振り被る与党政治家たちが、他の政策で「国民の理解」を常に軸足を置いてきたようにもみえないこともある。「国民の理解」を脇に置き、理解どころか国民の強い反発や異論のある政策を押し通してきたこととは、あまりにも、ちぐはぐであると言われても仕方がない。
国民の「納得」だとか「理解」とかいう言葉を、彼らは国民の中にある反発や異論を百も承知であるからこそ使う。だが、国民が「納得させられなかった」「理解を得られなかった」から、潔く断念するという場面にほとんど遭遇しない。つまり、この自体、国民の「納得」や「理解」を得るということは、彼らにとって、体のいいポーズ、結果とは関係ない、結論ありきの、ただの「やってる感」アピールということを物語る。
その同じ口が言う、「国民の理解が得られない」という言葉には、どうしても空々しさを感じてしまう。
しかし、一方でこれまで彼らが延々とこの言葉の効果を確信し、繰り出してきたことについては、もちろん彼らにそれを確信させてしまった国民や大マスコミにも、責任はある、と思う。政治家たちの「国民の理解」を掲げた努力を額面通り受け取ったり、前記したように果たしてそれが「国民の理解が得られない」ことかを徹底的に追及することをしない。なぜかそこにこだわらない姿勢がなかったか。
いわゆる「平成の司法改革」にあっても、この言葉しばしば登場した印象がある。とりわけ、司法修習生の給費制廃止問題では、「国民に理解が得られない」という言葉が、給費制維持を求める声に対して、散々浴びせられた。この言葉は、とりわけ税金の使い道に対する国民の反発を想定して(というかそういう描き方として)繰り出されることが多いが、同問題でも例外ではなかった。
つまり、裁判官、検察官はともかく、大部分が弁護士として民間の事業者になる弁護士に、本来自弁が当然である「職業訓練」に国費を投入するのは、国民が納得しないと。そもそも法曹三者として司法を支える弁護士の役割、それが公平に養成される意味を度外視して、司法修習をあたかも自ら稼ぐことになる弁護士のための「職業訓練」視することの問題性は、もっと議論されてよかった。
そして、そのことは通り一遍の説明も決め付けでなく、きっちりそれなりの時間をかけで伝えれば、果たしてそこまで国民が反対したり、「理解できない」ことだったろうか。結果として、この政策は一部修正されるが、今でも誤った「改革」として批判されている。これが、当の国民のためになっている、という評価も聞かない。
弁護士増員政策に絡む競争・淘汰を求める論調のなかでも、増員への慎重論に対し、弁護士を甘やかし、低廉化や良質化を阻害する不当な供給制限のように批判的にとらえ、あたかも「国民」対して「通用しない」といった指摘も度々出された。しかし、明らかに「国民」がそう考えて、求めたものではなく、「改革」よって描かれ、誘導されたものといっていい。
今にしてみれば、本当に増員が低廉化や良質化につながらないことを国民に伝えられていたならば、どうであったろう。利用者からすれば、無論、弁護士が経済的に恵まれていることを、当然のごとく「甘やかしている」などということにはならず、それが弁護士の経済的安定を崩し、今のようにカネに絡む不祥事発生や公的活動からの離反につながるならば、弁護士の経済的余裕はむしろ安全性担保のために歓迎してもおかしくない、ともいえるのである。
あえていえば、その意味では、理論的職能集団とされてきた弁護士会ですら、この「改革」の中で、前記のテーマの中で、「国民の理解」や「通用しない論」に徹底的に向き合って、その虚偽性について問い詰めることなく、従属させられてしまったということもできなくない。
政策推進者から繰り出される「国民の理解」という言葉は、もはやあまりに軽いものになっていると言ってもいいのかもしれない。権力者自ら「国民」を冠した政策や運動は、国民からは要注意だと言う人がいる。それと同様に、私たち自身が、彼らにご都合主義的な「国民」の利用を許していないか、まず、そのことにもっと敏感になるべきである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度をめぐる「市民感覚の反映」と「職業的自覚」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「電波停止」発言から考えるべき「受け手」側の弱点
- 編集長コラム「飛耳長目」~追及できない政治と司法への期待
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法務大臣」をめぐる慣行の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院、「無用」という実績への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「決められない」批判の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~死刑制度と裁判員制度への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「見直し」論のとらえ方と扱われ方
- 編集長コラム「飛耳長目」~大日本帝国憲法「復活」請願という状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~「関心」の背景にある閉塞状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~「弁護士インフラ論」をめぐる疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~「国防軍」が登場する改憲の欲求
- 編集長コラム「飛耳長目」~止められない「改革」への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「GPS」最高裁判決から学ぶべきこと
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員「配慮」という目くらまし
- 編集長コラム「飛耳長目」~「知る権利」担保を促す不信感
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍首相のなかの「軽視」と「怯え」
- 編集長コラム「飛耳長目」~歯止めなき国会で成立した歯止めなき法律
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種慎重論への扱いにみる危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判迅速化をめぐる変わらない懸念材料
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」の執念に対して求められること
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁く者」のフィロソフィ
- 編集長コラム「飛耳長目」~ジャーナリスト解放と日本の「自己責任」論の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制反対「バッシング」の「思い込み」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「捜査中」を言う答弁拒否の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~石破首相の「変節」を生んだもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法に及んできた政権の支配
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍自民、「改憲」加速化への不安要因
- 編集長コラム「飛耳長目」~「改革」アピールとしての「頼りがいのある司法」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「説明責任」と「納得」をめぐる現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「指揮権発動」騒動の不思議
- 編集長コラム「飛耳長目」~黙秘権の現実と大衆との距離感
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の体質を許してきたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験受験者「3000人」台時代到来が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権「暴走」を「許す」世論
- 編集長コラム「飛耳長目」~「獄死」という幕引きへの「意思」
- 編集長コラム「飛耳長目」~グロテスクな「予備試験」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~問われる「職務全う」論への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~量刑をめぐる「裁判員制度無理解」批判の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~警戒すべき選挙のご都合主義
- 編集長コラム「飛耳長目」~自民党派閥「裏金」疑惑事件の教訓
- 編集長コラム「飛耳長目」~憲法「争点化」をめぐる選挙状況が突き付けているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「停戦」を前提としない「支援」の見え方
- 編集長コラム「飛耳長目」~「闇バイト」を求める若者たちの「ハードル」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「改革」が想定していた社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~「砂川事件」最高裁長官「漏えい」問題の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~誤判・冤罪から問うべき「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「参入規制」批判のアンフェア
- 編集長コラム「飛耳長目」~9条がもたらした「不戦」への誇り
- 編集長コラム「飛耳長目」~「改革」と「法曹一元」の幻想