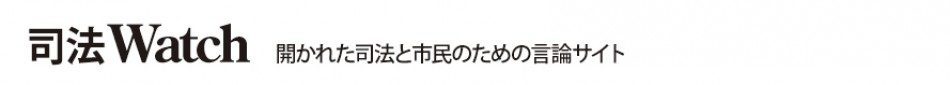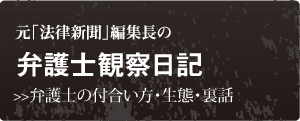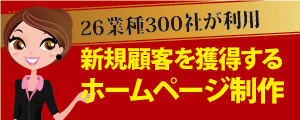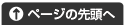司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
弁護士は社会のインフラである、という論調がある。捉え方そのものはいたってシンプルで、紛争解決、権利擁護、社会制度・ルールの監視といった弁護士の役割が、電気や水道といった物理的インフラと同様、社会が健全に機能するために不可欠といったものになる。
この見方は、いくつかの方向性をもった文脈で登場する。弁護士界外の人間が、弁護士にそうした役割の自覚を求める中で。また、弁護士会側が対外的に弁護士の役割を強調するなかで。更に付け加えれば、弁護士会主導層が、会員弁護士の自覚を促す中で。
しかし、弁護士の目線からすると、受け止め方はさまざまであり、「インフラ」という位置付けに、強い違和感を覚えるとする声もある。その最大の理由は、経済的基盤の問題である。端的に言って、前記物理的インフラ同様、本当に欠くことができないインフラとして、重視されているのならば、なぜ、その経済的基盤の安定化が議論の俎上に載らず、個人事業者である弁護士の経営努力に丸投げされているのか、という根本的疑問である。
そもそも弁護士は、国と対峙する刑事弁護は別にしても、民事にあっては、依頼者市民による受益者負担が原則のサービス業という捉え方も既に社会に定着している。そう考えると、前記いくつかの登場する文脈も、初めから通常のインフラとは違うことを前提に、いわば弁護士の経営努力のなかで「なんとかする」インフラという奇妙な使われ方をしているか、また、逆の立場は、そうした現実を分かっていながら、普通のインフラとの同列視への「願望」を込めて繰り出されているか、という風にもとれなくない。
いわゆる「平成の司法改革」にあっても、弁護士に競争原理を求め、一サービス業としての自覚を促しながら、採算性を一定限度犠牲にして、より公益性を求める形を成り立たせるような、ある種の無理・矛盾が見られるが、それに共通するものがあるようにもみえてくる。現実を脇に置いた「べき論」、イメーシや理想・願望先行の無理な表現ということもできてしまう。
しかも、やや不可解なのは、弁護士会の姿勢である。これを弁護士の社会的役割を対外的に強調する文脈で登場させる弁護士会主導層が、この現実を知らないわけではないことである。この文脈の向こうに、それこそ国費投入を含めた、本来的なインフラとしての経済的基盤の問題を真正面から取り上げるのならばともかく、そうではなくて、会内向けにインフラとしての自覚を促すとしているとすれば、それは分かっていながら、前記無理を飲み込む自覚を求めているようにとれてしまう。少なくとも会員間の冷めた意見には、そのように映る弁護士会主導層の姿があるようにも見える。
ところで、民事事件における弁護士業に関しては、現実的な疑問が湧いてしまう、このインフラという言葉を、仮に弁護士以外に当てはめるとすれば、何に当てはめるのが、よりしっくりくるだろうか。一つの見方は、民事執行法である。判決で確定した権利を実効たらしめる仕組みこそ、真のインフラではないか、と。
あくまで弁護士は権利を確定させるための手続きを支援する専門家であり、サービス提供者であり、当事者市民にとって、より根本的な仕組みである民事執行法こそ、よりインフラというべきではないか、ということになる。もっともこれをめぐっては、債権者の権利保護にとどまらず、債務者の人権保障、裁判所の人的・物的負担といったリソースの問題も言われ、これもまた「真のインフラ」として扱われるのには、それなりハードルが待っている。
弁護士の経済的基盤に対し、正面から国費を投入した、文字通りの「インフラ」として扱われるハードルに対し、そのハードル高低は比べようもないしかし、、いずれにしてもその名にふさわしい扱いが伴わないことへの関係者の疑問をはらみながら、それがなぜか正面から問われないまま、「弁護士インフラ論」だけが流通している奇妙な現実である。
- 編集長コラム「飛耳長目」~「緊急事態」下の「優先順位」と弁護士の存在価値
- 編集長コラム「飛耳長目」~すべてを物語る自民憲法改正草案「前文」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「獄死」という幕引きへの「意思」
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹養成に絡めて登場した国会議員の危い司法観
- 編集長コラム「飛耳長目」~「別の目的」で動く人たちへの目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~新しい刑事司法への思惑と目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~見極めるべき法科大学院「失敗」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヘイトスピーチ」対策口実化の危険
- 編集長コラム「飛耳長目」~「パブコメ」不信がもつ意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~本当の危機感が伝わってこない「改革」路線維持
- 編集長コラム「飛耳長目」~「疑わしきは裁判」という時代の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「安倍暴走」のブレーキ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「見直し」論のとらえ方と扱われ方
- 編集長コラム「飛耳長目」~欠陥としての検察の証拠不開示
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「やってる感」
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員「良い体験」ストーリー報道のアンフェア
- 編集長コラム「飛耳長目」~「砂川事件」最高裁長官「漏えい」問題の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~「強行採決」国会を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「参入規制」批判のアンフェア
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権「暴走」を「許す」世論
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法案反対、学者・日弁連共同記者会見で示された認識と現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~女性閣僚「在特会」会見の深刻度
- 編集長コラム「飛耳長目」~「司法改革20年」、朝日「社説」から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制成立強行での「軽視」が残したもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヒラメ」が増殖する裁判所体質
- 編集長コラム「飛耳長目」~派遣法改正という「規制緩和」の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~「翼賛」という言葉があてがわれた「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「検察刷新会議」に問われているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「知名度選挙」という病
- 編集長コラム「飛耳長目」~権力を疑う目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「自粛警察」登場が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~大日本帝国憲法「復活」請願という状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田政権がみせた国民との「断絶」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「マスク社会」が映し出しているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~民意の偽装が教える現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~公文書改ざんが罷り通る国のムード
- 編集長コラム「飛耳長目」~緊急事態宣言下の五輪開催が示すこの国の病
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度の「本末転倒」というツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「市民のための『改革』」の現実と責任
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ対策便乗マイナンバー拡大策の胡散臭さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~記録を残さない安倍政権の心底
- 編集長コラム「飛耳長目」~支持率に対する政権の姿勢から読み取るべきこと
- 編集長コラム「飛耳長目」~「難民」に対する本当の目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~ウクライナ戦争で突き付けられた9条をめぐる「選択」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「仮定の話」という回答拒否論法の悪質さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「終わりの始まり」の年を送って
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の体質を許してきたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「STAP騒動」にみる「権威」の中の油断と軽視
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判IT化の流れと弁護士をめぐる懸念
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪組織委会長辞任劇が映し出したもの