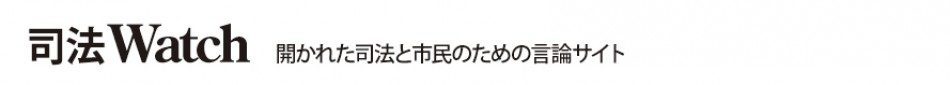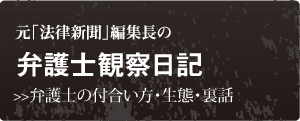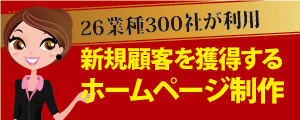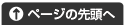司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
SNS上に溢れている石破茂首相に対する批判的な声の中に、「決められない政治」という文言が多くみられることに複雑な思いが湧いてくる。いうまでもなく、政権が少数与党という現実を抱えていることもあるが、世論調査での内閣不支持の理由の上位に、「実行力のなさ」という彼の資質によるととれる意見が入る。就任早々、前言を覆したととれる「変節」を印象付けてしまったことも響いているという見方もある(NHK世論調査 「石破首相の『変節』を生んだもの」)。
しかし、違和感を覚えるのは、そこではない。相変わらず「決められる政治」を求め、「決められない政治」を悪とするような、国民の中にあるとらえ方と目線についてである。安倍・菅政権で国民は何をみせられてきたのか、ということをどうしても問いたくなってしまうのである。
もはや繰り返すのも妙な気になるが、彼ら自民党政権が、民主党政権批判のなかでも、あるべき形として最上段に振りかぶってきた「決められる政治」の正体とは、批判や議論を求める声に耳を貸さない政治だったことを、国民は安倍・菅政権で目の当たりにしたはずだ。
そして、それは逆に「決められない政治」であればあるほど、政権は熟慮や議論を余儀なくされることであり、むしろそれによってより民主主義的な政治も担保されることが痛いほど明らかになったことも意味した。それは、同時にあたかもこの国の政治、あるいは国民にとってふさわしいと彼らが強弁してきた「決められる」が、実は自らの権力行使と独裁にふさわしいものとして求めていた、といういわば、化けの皮も剥がれたはずなのである。
それでもなお、「決められる政治」を求める国民の心情には、一体、何を見るべきだろうか。一つには、もちろん国民の中にあるこの国に対する閉塞感はあるだろう。何かを変えてくれるのは、「決められる」政治家であるという待望論が、前記反民主主義的な、熟慮と議論を顧みない政治への警戒感を曇らす。
そこには、「強いリーダーシップ」といった表現で、より「決められる」ことの方をより肯定し、それへの警戒感を喚起しない大メディアの取り上げ方の影響も大きいようにとれる。「決められない政治」の問題性を、政治に対する善意解釈でとらえれば、当然、国民にとって有意な政策が、実行できず、停滞してしまう弊害を言うことになるが、多くのメディアが、それと比した反民主的な決定の弊害、それによって失われるものの大きさをフェアに扱っていないようにとれる。つまり、「国民にとって有意な政策」という前提に立つ見方が、そもそもその前提を議論するプロセスの問題を看過しているような印象すら持つ。
もう一つは、要素は分断だろう。既に世論の分断を受け入れ出している国民の多くが、民主主義的な包摂的な議論に価値を見出さず、一足飛びに何かを実現する政治を期待しているということである。しかし、大きな反動が予想される民主主義的な危機ともいえる。それこそ「強いリーダーシップ」に牽引され、それに盲従することで、気が付けば、後戻りができない民主主義の崩壊を招く恐れがある。反対論を付け合わす議論とそれに基づく熟慮によって、国民も思い込みから目覚め、自らを正しい判断に軌道修正する可能性はないだろうか。
石破首相が「決められない」ことで、我々には得られることもあるのではないか。もし、「決められる」状況ならば、今の政策・懸案に対する議論状況は違っていたはずだ。「決められない」といことが、数によって強行するという熟慮と議論を回避する手法を打たせないこと、そして、本来的には意見が分かれるということそのものに、回避すべきではない議論の余地があるということを考えれば、むしろその健全さを我々は感じるとるべきではないか。
その意味では、国民の中から頭をもたげる「決められない政治」批判そのものにも、我々は注意深く、見つめていく必要があるように思えてならないのである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~「翼賛」という言葉があてがわれた「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~組織的不正を止められない官僚の体質的構造
- 編集長コラム「飛耳長目」~果たされない「説明責任」と自覚の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法書士「活用」路線の期待と現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹人口増員論議のステージ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定が教えている深刻な司法機能不全
- 編集長コラム「飛耳長目」~「獄死」という幕引きへの「意思」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「排除」失速劇が映し出したもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~検事長定年延長問題で問われていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~「良い忖度」の罠
- 編集長コラム「飛耳長目」~「忖度」の不自然さからみる公文書改ざん事件
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度9年から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「電波停止」発言から考えるべき「受け手」側の弱点
- 編集長コラム「飛耳長目」~「独立性」の価値というテーマ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「高市発言」を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ゴーン被告人逃亡」と「人質司法」の悲観的な展開
- 編集長コラム「飛耳長目」~「後進国」日本に問われているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「資格」の責任、「改革」の責任
- 編集長コラム「飛耳長目」~グロテスクな「予備試験」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~メディアによる「停戦」の使い分け
- 編集長コラム「飛耳長目」~迷走答弁から見える安倍政権の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~新法曹養成制度維持にとっての苦しい「活路」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「弔意」が強制される国
- 編集長コラム「飛耳長目」~「反社会的勢力」定義問題が示す危険度
- 編集長コラム「飛耳長目」~メディアのアンフェアと大衆の立ち位置
- 編集長コラム「飛耳長目」~「市民のための『改革』」の現実と責任
- 編集長コラム「飛耳長目」~トランプ政権の暴走と日本の現実から捉えるべきこと
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍日本で懸念すべき、もう一つの「副作用」
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹の「質・量」確保論の行方
- 編集長コラム「飛耳長目」~「先導的法科大学院」という期待の形
- 編集長コラム「飛耳長目」~伝えられていなかった裁判員制度のツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「露骨」な秘密保護法案
- 編集長コラム「飛耳長目」~岡口罷免判決への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「稲田発言」への反応と戦争へのハードル
- 編集長コラム「飛耳長目」~NHK受信料訴訟をめぐる違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「無辜の処罰」を回避する司法との距離
- 編集長コラム「飛耳長目」~想像力「封印」という危機
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院の制度的「無理」という視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~「自粛要請」がもたらしている危険な兆候
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍首相の「リーダーシップ」と「独裁」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「戦争法案」発言で再びみせた安倍タイプ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「終わりの始まり」の年を送って
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院、「無用」という実績への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田首相発言にみる「責任」の空文化
- 編集長コラム「飛耳長目」~黙秘権の現実と大衆との距離感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「18歳裁判員」と変わらない「改革」論調
- 編集長コラム「飛耳長目」~民意の偽装が教える現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~すべてを物語る自民憲法改正草案「前文」
- 編集長コラム「飛耳長目」~警戒すべき選挙のご都合主義
- 編集長コラム「飛耳長目」~ジャーナリスト解放と日本の「自己責任」論の正体