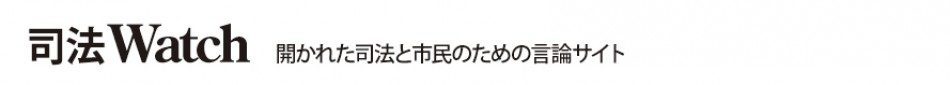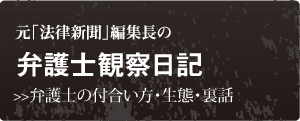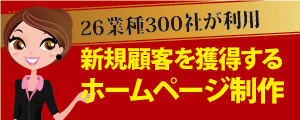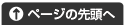司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
2025年の司法試験合格者が11月12日に、発表されたが、出身別での合格率は、相変わらず、どの法科大学院よりも司法試験合格組が圧倒的に群を抜いている(本年実績でトップの京都大学が58.45%、法科大学院平均34.26%に対し、予備試験合格者90.68%)。
しかし、もはやこの「異常性」が大マスコミの報道などでほぼ言及されない。同日付の日弁連会長談話でも全く言及されていない。司法試験におけるこの状況は制度開始以来、固定化しており、既に当時予備試験組の合格率はほぼ7割、近年は90%台を推移し、法科大学院との差は不動のものになっている。
既に見慣れた光景という観すらするが、いうまでもなく、それで済む問題でないのは明らかはずだ。本道を自負している法科大学院修了レベルが、予備試験組合格者のレベルに遠く及ばないという現実は、司法試験制度改革根幹の矛盾、あるいは失敗を露呈しているという評価になるからである。
よく予備試験組は予備試験という厳格な関門を経た人材なのだから、結果的に合格率が高くなるのは当然、という形でこの問題をとらえる人がいる。しかし、いうまでもなく、予備試験合格者のレベルが法科大学院修了者のレベルと同等という話どころか、圧倒的に上回り、固定化しているという現実は、制度からすれば、本道を自負する制度である以上、明らかに「異常」と断じない方がおかしいし、それに言及しないことそのものが「異常」なのである。
二つの見方ができる。一つはいわゆる「入口」の問題。つまり、法科大学院入学の時点、厳格な選抜を行っていないことが、この結果につながっている、という見方である。しかし、そもそもの制度の理念と抵触しかねないという問題もある。つまり、「多様なバックグラウンド」の人材を法曹に育てることを掲げた制度が、例えば、予備試験レベルとはいわないまでも、入口時点で厳しい関門を課すことには制度側に相当な抵抗があるし、そもそもそれでは生徒が集まらない、という話になる。
そうなると、やはり法科大学院というプロセスの「実力」の問題としなければならない。現在の基準で「入口」で採用した人材を、法科大学院の理念に基づく教育を施しても、予備試験組ほどのレベルにすることができない、という法科大学院の「実力」であり、「実績」の問題である。
さらに、根本的な問題といえることもある。仮に理念にこだわった法科大学院の教育を施した結果、司法試験合格率で予備試験組に敗北したとしても、その法科大学院修了の法曹が、予備試験組法曹との比較において、何らかの有意な質的な差があるということであれば、制度理念の面目は立つ。その時、はじめて現在、法科大学院関係者からも時々聞かれる、司法試験元凶説にも説得力が出で来るかもしれない。
しかし、現実はいまだそういう社会的評価はない。それどころか、むしろ難関を越えてきた予備試験組法曹の方が「優秀」という社会的評価も一部に聞かれる。これでは、理念の教育の効果で、法科大学院側が弁明することも、現在のところできない。
旧司法試験を「一発試験」として、あれほど法科大学院を挟んだプロセスの教育の効用を強調した「改革」が、それを実証できていない。つまりは、現在のところ、予備試験の圧倒的な実績によって、むしろ「一発試験」選抜が法曹輩出に遜色ないことが証明されていることになるのだ。
では、なぜ、むしろ誰でも受験できるというメリットもあった旧司法試験体制に戻さないのか、戻せないのか。法科大学院制度を直ちに廃止しなくても、修了者の受験条件化を外し、自由に選択できる制度になぜ、踏み切れないのか。
大きく分ければ二つの理由ということになる。一つは、あくまで前記「改革」が掲げた「理念」の正しさにしがみつく意見。つまり、「一発試験」では得られない法曹に必要な実務的素養や倫理観などが培われる過程として、あくまで制度の重要性の主張を繰り返すものである。しかし、前記してきたように、既に14年か経過しても、それは実証されていない。
この間、行われた制度見直しでは、大学・大学院一貫5年の法曹コースや大学院在学中受験容認といった、法曹までの「時短化」という、予備試験人気を意識した、いわば同試験との競争条件を有利にしようとするもので、同じ制度擁護派からも「理念をかなぐりすてている」という批判が出たものだった。「理念」の説得力で勝負できないことを、少なくともこの見直しを進めた関係者は、この時点で、実は十分に認識しているようにもとれた。
そして、この理由が実質的に苦しいとなれば、残るのはただひとつ。既に制度を作ってしまったことへのこだわり、別の言い方をすれば、特定のステークホルダーの生存戦略の壁ということになる。
本来、理念が正しいと言い続けるのであれば、前記したように予備試験を廃止して、旧来の誰でも受験できる司法試験を復活させ、それでもなお、法科大学院が輩出法曹の能力の有意な差で、理念の教育の正しさを実証する道を選んでもいいはずだ。しかし、制度にはそこまでの自信はない。
それでも制度を続けることが、あるべき法曹養成なのか――。予備試験組の司法試験合格率が示し続けている、法科大学院制度と法曹養成にとっての決定的な現実に目が向けられない「異常」な状態が続いている。
- 編集長コラム「飛耳長目」~「丁寧な説明」と「国葬」強行が示す劣化
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」再審無罪が断罪した司法の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヒラメ」が増殖する裁判所体質
- 編集長コラム「飛耳長目」~「マスク社会」が映し出しているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~菅首相「多様性」発言の真意
- 編集長コラム「飛耳長目」~問われる「職務全う」論への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験漏洩再発防止策検討と「資質」の断念
- 編集長コラム「飛耳長目」~弁護士による横領という末期的状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~戦争という手段が「常識化」した世界
- 編集長コラム「飛耳長目」~議論に乗る危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法書士「活用」路線の期待と現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~取り調べ「全過程可視化」への抵抗を許すもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定が教えている深刻な司法機能不全
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度見直しの発想と無理
- 編集長コラム「飛耳長目」~「止めてはならない戦争」という価値観
- 編集長コラム「飛耳長目」~ネット発言の実名主義と責任への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験結果からみる政策的「努力」の意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~「強行採決」国会を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「関心」の背景にある閉塞状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~「国民の理解」登場のご都合主義と軽さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~派遣法改正という「規制緩和」の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田政権がみせた国民との「断絶」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「砂川事件」最高裁長官「漏えい」問題の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種誘導に専門家が「物語性」を求める現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹人口増員論議のステージ
- 編集長コラム「飛耳長目」~果たされない「説明責任」と自覚の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍首相のなかの「軽視」と「怯え」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「自粛要請」がもたらしている危険な兆候
- 編集長コラム「飛耳長目」~記録を残さない安倍政権の心底
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹養成を大学運営に委ねたツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~変わらない「犯人視報道」
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種慎重論への扱いにみる危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~女性閣僚「在特会」会見の深刻度
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度擁護派に欠落した発想
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判でまかり通る現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~グロテスクな「予備試験」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~トランプ政権の暴走と日本の現実から捉えるべきこと
- 編集長コラム「飛耳長目」~小沢控訴審判決と司法の役割
- 編集長コラム「飛耳長目」~「良い忖度」の罠
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種と情報公開への危機感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法務大臣」をめぐる慣行の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~抵抗する責任、問い直す責任
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院、「無用」という実績への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~結果責任を問わない「改革」推進姿勢の絶望
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪開催をめぐる言葉に表われたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~能登支援「寄付」と裏金問題を繋げる政治家の感性
- 編集長コラム「飛耳長目」~責任が問われない裁判官という地位への自覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~改革にカギかっこを付けられる弁護士会
- 編集長コラム「飛耳長目」~民意の偽装が教える現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新しい人権」論議の胡散臭さ