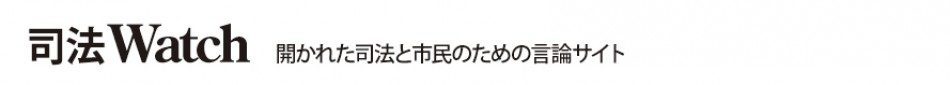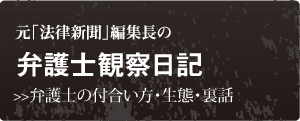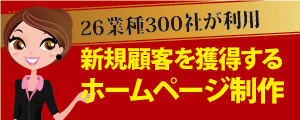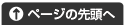司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
「平成の司法改革」の失敗が、いろいろな面で明らかになってきたころから、法科大学院関係者あるいは制度擁護者に対して、弁護士界の中から異口同音に言われてきたことがある。
「弁護士に競争、競争という割に、自分たちが競争にさらされているという自覚や覚悟がないのではないか」
これは、弁護士側から彼らに向けられた、ある種の皮肉であると同時に、実に現実を鋭く突いた言葉といえる。激増政策の失敗による、弁護士の競争激化と経済的悪化の現実は、法科大学院が「改革」で法曹養成の中核と位置付けられた以上、本来、志望者の輩出先であり、かつ、法曹養成への先行投資へのリターンに関わることであるならば、法科大学院関係者にとって、強い関心を抱いてよいテーマであるはずだった。
ところが、現実は冷ややかで、あたかもそれは法曹養成とは関係ない、弁護士界がなんとかする問題であるかのような態度とともに、ひたすら競争を受け止めよ、というような姿勢だった。その背景にあるのは、弁護士側の激増政策批判への牽制。つまり需要の非顕在化の現実から、司法試験合格者減の方向が導かれることが、法科大学院の生存にマイナスであることを、いわば近視眼的に恐れた結果ともとれた。
志望者減という結果から考えれば、この近視眼的思考は明らかに間違っている。「改革」によって、法曹養成の中核と位置付けられた以上、法科大学院制度自体が、いくつもの競争への自覚を抱え込んでいなければならないはずだったからだ。まず、根本的なことからいえば、新たな法曹養成のプロセスが、志望者によって選ばれるという、進路選択上の競争である。新たに時間的経済的負担、それに見合う結果をプロセスは提供してくれるのか、という問題である。
この話をすると、関係者の中には、すべてを前記したような合格者数に責任転嫁するような反応が返ってきたりもする。すべてはいまだ合格させない司法試験が悪い、われわれは悪くない、というように。しかし、合格者年3000人目標の撤回は、需要の問題とともに、新制度における質の担保に疑問がなかったわけではない(「増やしたくても増やせなかった司法試験合格者」)。
しかし、それもさることながら、本来、あれほど旧司法試験体制を批判して構築された制度であるならば、輩出された法曹の質において、有意な差を示すことは、新制度が背負った責任でもあるはずだった。しかし、そういう責任への自覚が果たして制度側から示されたであろうか。そもそもその責任への自覚や覚悟、あるいは自信があるならば、それこそ修了を司法試験の受験要件とする形に、あたかも手放せば、志望者を失うかのごとく、しがみ付くこともない。堂々と実績で、志望者に選ばれる道を目指すことこそ、あるべき自覚ともいえる。
具体的な競争相手として、彼らが自らの本道主義を最上段に振りかぶって目の敵にする予備試験、旧試験体制に関連して「依存」などという言葉で批判した予備校も、本来、彼らが堂々と実績で勝負していい相手である。新制度が実証的にその実績で、彼らと競争することが、本来彼ら推進者が、この「改革」で背負ったものであったはずであるが、その自覚が彼らからは残念ながら今日に至るまで感じられない。
「選ばれる側の自覚」の欠如という意味では、もう少し広い意味で、この「改革」と法曹界自体発想の歪みにも指摘できる。一口に言えば、職業としての法曹人気への過信である。新たな経済的時間的負担を課すプロセスを半ば強制しようとも、その経済的なリターンが弁護士の経済環境悪化で厳しくなろうとも、おまけに司法修習生の給費制を廃止しようとも、志望者はこの世界の門をたたく、と。法科大学院関係者だけではなく、法曹自体にもその過信はあったようにとれる。別の言い方をすれば、資格の経済的価値の軽視にもとれる。
結果、志望者減が深刻な形になるまで、彼らは完全にその過信の中にいた。しかし、法科大学院関係者は、その現実が突き付けられても、予備試験への志望者流出を意識し、同ルートとの競争条件として、資格取得への時短化という、一転というか、ある意味、一層本質的な、実績での勝利を目指すものではない、見直しまで打ち出し、制度理念の正しさを信じてきた一部支援者からも批判される結果となった。
しかし、これでもなお、まだ制度をなんとか維持しようと思っているのであれば、彼らはいまだ過信の中にいる、いうべきなのかもしれない。競争への自覚がないといったが、それはそもそも制度実績で勝負して、それによって存在を評価されるという自覚そのものがない、という現実を反映しているのである。
そして、なおかつ、最も肝心なことを付け加えるのであれば、それはあくまで「平成の司法改革」で構築された新制度の維持から逆算する発想であって、あるべき法曹養成から逆算されているわけではない、ということも、直視しなければならないはずなのである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員「配慮」という目くらまし
- 編集長コラム「飛耳長目」~選挙結果に反映しなかった「危機」のリアリティ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「敵味方刑法」の影
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」再審無罪が断罪した司法の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「戦争」と「軍事行動」を区別する危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁く者」のフィロソフィ
- 編集長コラム「飛耳長目」~ハンセン病家族訴訟、「政治決断」への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「GPS」最高裁判決から学ぶべきこと
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法科大学院」という止まらない列車
- 編集長コラム「飛耳長目」~死刑廃止問題と弁護士会内民主主義の狭間
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の体質を許してきたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~黙秘権の現実と大衆との距離感
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院の制度的「無理」という視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~「順法精神」利用への危機意識
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「強制閉校」方針が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法案反対、学者・日弁連共同記者会見で示された認識と現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権下の公文書問題と「隠ぺい」
- 編集長コラム「飛耳長目」~死刑制度と裁判員制度への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~問われる「職務全う」論への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~ウクライナ戦争で突き付けられた9条をめぐる「選択」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「社会放出」論が軽視するものと、その目的
- 編集長コラム「飛耳長目」~元裁判官の司法改革批判からみえたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~NHK受信料訴訟をめぐる違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~新しい刑事司法への思惑と目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~選択的夫婦別姓が実現しない国の実相
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍日本で懸念すべき、もう一つの「副作用」
- 編集長コラム「飛耳長目」~石破首相の「変節」を生んだもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~国民を「なめている」政治
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制がもたらそうとしている「分かりやすい」危機
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ウクライナ戦争」とわが国で起きていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~組織的不正を止められない官僚の体質的構造
- 編集長コラム「飛耳長目」~「翼賛」という言葉があてがわれた「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「全能感」という宿痾
- 編集長コラム「飛耳長目」~南海トラフ地震「注意」喚起と社会実験
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」をめぐる執念と侮り
- 編集長コラム「飛耳長目」~ジャーナリスト解放と日本の「自己責任」論の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度が抱えた矛盾と甘え
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度からみる「徴兵制」
- 編集長コラム「飛耳長目」~高市「解散」が投げかけた「白紙委任」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「予備試験」制限という法科大学院「強制」の末路
- 編集長コラム「飛耳長目」~「弔意」が強制される国
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権「暴走」を「許す」世論
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」一審裁判官の告白が投げかけた重い課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~法学研究者養成の危機が示す「改革」の現在
- 編集長コラム「飛耳長目」~「止めてはならない戦争」という価値観
- 編集長コラム「飛耳長目」~バラツキを生み出した法科大学院制度の根本的発想
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹人口増員論議のステージ
- 編集長コラム「飛耳長目」~多様性への不誠実さという視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判「尊重」最高裁判決が示す状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~自民・政治資金規正法改正で見えた本性