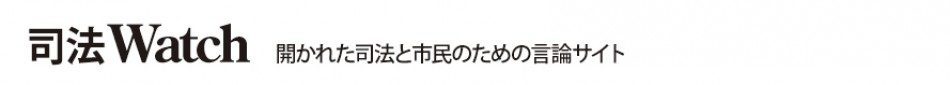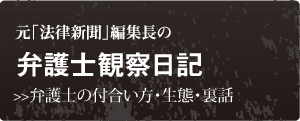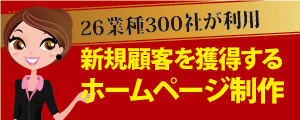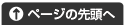司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
NHKをはじめとする大手メディアが、先の大規模な「財務省解体デモ」を報じず、この度の「石破(首相)辞めるなデモ」を大きく報じていることに、SNSなどで強い疑問や批判の声が出でいる。あまりに分かりやすい偏向報道ではないか、という話である。
メディア側にどういう弁明が用意されるかは、だいたい想像できる。メディアのニュースバリューの判断にあっては公共性、影響力、新規性、視聴者の関心度などが考慮されるところ、「石破辞めるなデモ」は現職首相の去就に関わり関心が高く、一方「財務省解体デモ」は、主張の過激さ、実現可能性からバリュヘー低く判断した、とか。あるいは後者については、具体的な政策提言が不足しているとか。メディアの限られたリソースのなかで、何を優先的に報じるかの選択は必要であり、この優先順位は、そこまで不当とはいえない、とか。
しかし、一方で、こうしたメディアが用意しそうな弁明は、この件への反応が象徴するような、既に国民の中に広がりつつある、いわゆる「オールドメディア」への不信感に、ほとんど無力であるといっていいだろう。そのことをメディア側はどうとらえているのだろうか。
いうまでもなく、ニュースの恣意的な取捨が問題になっているときに、従来からメディアが掲げてきた一般的な「判断基準」を弁明とすることは、あまりに形式過ぎて意味をなさない。公共性や影響力そのものの判断で異を唱える国民との間にはもちろん認識差がある。とこまでいってもその認識差を無視し、メディアのニュース選択の結果に、逆に基準を被せて答えているとしか、国民には見えない。
問題視する国民からすれば、当然、メディアの基準の弁明が聞きたいのではなく、国民の仮に一部にでも、そういう論調とそれに基づく行動があることをフェアに報じる役割はメディアにないのか、という話になる。彼らからすれば、それがフェアに報じられれば、国民の問題意識も変わるかもしれない、と考えておかしくない。そして、それが意図的に国民の気付きを阻害する行為とみるからこそ、偏向批判が生まれている。
しかも、この二つのデモは、メディアの判断基準への信用度を上回るほど、はっきりと国民に伝わる正反対の、分かりやすいベクトルを持っている。国民の中に広がる減税要求。それに対し、はっきりと後向きな石破政権の存続と、減税を阻む問題の根源とされる財務省の解体要求。二つのデモの一方が報じられ、一方が報じられないことが、どちらのベクトルを利するかはもはや明確であり、それを単なる疑念として形式的ニュースの選択基準をもって片付けることは、あまりに無理がある。
財政健全化を使命としている財務省の「解体」を言う主張は、財政健全化の議論を阻害する可能性がある、とも、メディアは言うかもしれない。しかし、これも国民の声を公平に取り上げるというスタンスを後方に押しやる理由になるだろうか。もちろん異を唱える国民に通じるわけもない。そもそもいま、減税要求をみれば分かるように、国民が今、財政健全化の議論を優先させるべきかどうかで意見が分かれていることには、フェアな対応は必要ないというのだろうか。
メディア側からは、お決まりの報道基準の公開と説明、編集方針の明確化によって、国民の「誤解」を解くという方向が出てくるように思う。しかし、これは実質、メディアは今起きていることを直視し、自らの姿勢を変えることを意味しない。とてつもない今起きている国民の離反への楽観的な姿勢になるだろう。
メディアが何を取り上げ、何を強調して報じるかによって、社会の中で何が重要として認識され、大衆の関心がどこへ向くか、の左右される効果にとして、最近「アジェンダセッティング効果」という言葉が言われる。この言葉は、メディアからすれば、例えば「財務省解体デモ」の非現実性や過激さの強調への抑制的姿勢の根拠として使われるかもしれない。
しかし、これは全く逆の意味合いで、メディアへの警戒感を煽るものにもなるだろう。「報道しない」大義名分が当てはめられたとしても、国民の意識を問題から遠ざける効果をはらみ、それを自覚したメディアによる、偏向報道の温床と捉えられる可能性は十分にあるからだ。この効果があればこそ、危険なのだ、という主張になり得る。
メディアは、その報道姿勢に対する国民の目線に対し、いまだ相当楽観視しているようにしか思えないのである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~偏狭的ナショナリズムによって失われるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「負の遺産」としての「成功体験」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共同」憲法世論調査からみえる状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法案「理解不足」論が示しているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「司法改革」を求める市民目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「強制閉校」方針が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~武器輸出拡大とわが国が守ってきた「価値」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「司法改革20年」、朝日「社説」から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「日本人ファースト」をめぐる分断
- 編集長コラム「飛耳長目」~「戦争」と「軍事行動」を区別する危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権「暴走」を「許す」世論
- 編集長コラム「飛耳長目」~「関心」の背景にある閉塞状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~メディアの扱いに差が生まれた2つのデモ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ワンイシュー」批判から見える逆の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~投票「日当制」提案が映し出す現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「決められない」批判の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院在学中受験の効果と意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪組織委会長辞任劇が映し出したもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~原発国賠訴訟最高裁判決が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~問題言動の「謝罪」にみる無意味性
- 編集長コラム「飛耳長目」~マスメディア批判と「両論併記」の努力
- 編集長コラム「飛耳長目」~派遣法改正という「規制緩和」の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判「協働」の無理と危さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~権力を疑う目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~元首相暗殺と旧統一教会問題から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~多様性への不誠実さという視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「やってる感」
- 編集長コラム「飛耳長目」~NHK受信料訴訟をめぐる違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁判員バッジ」が象徴する制度の無神経
- 編集長コラム「飛耳長目」~ウクライナ戦争で突き付けられた9条をめぐる「選択」
- 編集長コラム「飛耳長目」~追及できない政治と司法への期待
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種慎重論への扱いにみる危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制成立強行での「軽視」が残したもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法の支配」を登場させた法曹養成「改革」提案
- 編集長コラム「飛耳長目」~「露骨」な秘密保護法案
- 編集長コラム「飛耳長目」~「検察刷新会議」に問われているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~注意すべき「利用しやすい」民事司法改革論議
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制、強行採決で見せつけられている現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~伝えられていなかった裁判員制度のツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~平和主義と民主主義への危機感
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度、「市民感覚」のあいまいさという問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~「利用されない」ことを恐れる「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~伊方原発差し止め高裁判断と福島事故の教訓
- 編集長コラム「飛耳長目」~検事長定年延長問題で問われていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~正気を失わないために
- 編集長コラム「飛耳長目」~刑事司法への警戒感不足という現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「止めてはならない戦争」という価値観
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験受験者「3000人」台時代到来が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ファクトチェック」の正統性への疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヘイトスピーチ」対策口実化の危険