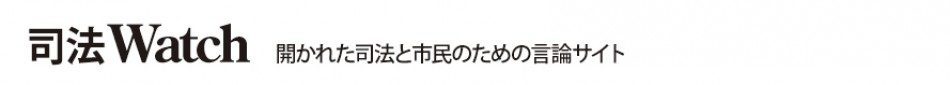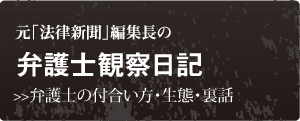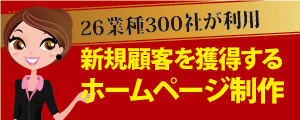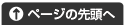司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
法科大学院制度が掲げた、というよりも、正確には同制度に被せられたというべき「理想」を礼賛する声が、制度発足からずっと聞かれてきた。
質・量ともに豊かな法曹を輩出するため、受験技術偏重や予備校依存を改め、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスの法曹養成が必要で、その中核として法科大学院が必要かつ有効。法曹に共通して必要とされる専門的資質・能力の習得と、かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して深く共感しうる豊かな人間性の涵養、向上を図る。社会人等としての経験を積んだ者を含め、多様なバックグラウンドを有する人材を多数法曹に受け入れる、等々。
大学関係者はもちろん、「改革」で制度の旗を振る側に回った法曹関係者や大マスコミも、ことある毎に、こうした制度の「理想」を繰り返し持ち出してきた。この「理想」は正しい、決して忘れてはいけない、と。ただ、一方で、このこと自体が、ある時点から、奇妙な印象を与えるものになっているようにとれるのだ。つまり、この制度の現実、実績に対する厳しい見方に対し、その根本的な原因と切り離した形で、この「理想」が強調されるのを目の当たりにすることになっているからだ。つまり、「それでもこの『理想』は正しい」と。そこに救いを求めるかのように。
一見すると、そこに描かれている一つ一つのものは、まさに「理想」のようなものであっても、現実や実績から逆算すると、それは本当に制度にとって現実的に「理想」だったのか、いや、制度はあくまでこの「理想」を建て前に、実は別の目的で進められ、まさにその結果こそが、今の制度の現実ではないか、という疑念が湧いてくるのである。
プロセスと銘打ってはいるが、旧制度にも存在した「プロセス」(司法試験・司法修習)に比して法科大学院を中核とする法曹養成は、本当に「理想」足り得ているか、受験技術偏重、予備校依存への批判にしても、輩出された法曹の質から、制度は実績としてその正しさを証明できたのか。制度が目指した法曹の質の向上について、実績としての社会的評価は得られ、また、定着しつつあるのか。人材の多様性を挙げながら、そもそも制度としてのプライオリティは本当に高かったと言えるのか――。
現実から逆算しないことによって、「理想」は「理想」として、胸を張り続けられ、同時に決して制度が担った本当の目的(あるいは優先事項)にはたどり着けない、たどり着けさせない、そんなカラクリがあるようにさえ見えてくる。
法科大学院開設20年で、久々に朝日新聞が社説で制度について取り上げたが、この中にも、制度存続ありきから逆算した結果といえるような、奇妙な取り上げ方が登場する。前記したような制度の理想から、お決まりの制度発足後の想定をこえる74校の乱立、司法試験合格率の低迷、志望者減、大学院の撤退、生き残りをかけた司法試験合格率向上のための「予備校化」、人気回復のための「法曹コース」や在学中の司法試験受験容認という現実の振り返り。
「失敗」ともいえる制度のそうした紆余曲折が、なぜ、前記「理想」の旗のもとで起きたのかは一切振り返ることなく、「朝日」はある「学生に表れた変化」に注目する。司法試験後、経験を積むために刑事事件容疑者に接見したり、一般の人の法律相談に乗る活動に参加する学生が増え、コミュニケーション力の大切さに気付いたり、将来の活動分野を社会的弱者への支援に変えたりする学生もいる、と。
そして、「朝日」はこうつなげている。
「まさに法科大学院が本来めざすべき教育に自発的に取り組もうとする、頼もしい動きだ。各校は、こうした学生の行動を後押しする教育に力を入れるのが本筋である」
正直、一瞬、何を言っているのかと、目を疑った。もとよりこの学生の行動自体は正しく、望ましいものであっても、それは「理想」を掲げた制度の実績とは直接関係ない(少なくとも関係は示されていない)。「本来めざすべき教育」にあくまで自発的に取り組んでいる学生たちの姿を取り上げているにすぎないし、「本来めざすべき教育」という話も、「後押しする教育に力を入れるのが本筋」という話も、まさに制度の現実からは隔絶した、あまりに唐突な話である。
語るべきことを脇に置き、またぞろ制度の現実とは切り離された「理想」の話である。「朝日」はこの社説のタイトルに「取り戻したい本来の姿」とうっているが、それこそ制度ありきの発想の果てに表れた、大衆の目を逸らさせる意図を感じさせる、この制度をめぐる「理想」の使い方の典型例のように思える。
もはや騙し絵のように、現実の姿とは隔絶した、「理想」の姿を大衆に見せようとする試みが延々と続けられる限り、現実的で可能な、あるべき法曹養成への本当の議論は始まらない。
- 編集長コラム「飛耳長目」~国民の強制動員からみるウクライナ戦争
- 編集長コラム「飛耳長目」~「知名度選挙」という病
- 編集長コラム「飛耳長目」~検事長定年延長問題で問われていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~団藤重光氏が伝え残した「葛藤」
- 編集長コラム「飛耳長目」~高市「解散」が投げかけた「白紙委任」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」一審裁判官の告白が投げかけた重い課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~「戦争」と「軍事行動」を区別する危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員「配慮」という目くらまし
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヒラメ」が増殖する裁判所体質
- 編集長コラム「飛耳長目」~バラツキを生み出した法科大学院制度の根本的発想
- 編集長コラム「飛耳長目」~追及できない政治と司法への期待
- 編集長コラム「飛耳長目」~低投票率が示す本当の深刻さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法案反対、学者・日弁連共同記者会見で示された認識と現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験受験者「3000人」台時代到来が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~女性閣僚「在特会」会見の深刻度
- 編集長コラム「飛耳長目」~行き場を失っている裁判官への信頼
- 編集長コラム「飛耳長目」~「捜査中」を言う答弁拒否の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~元首相暗殺と旧統一教会問題から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~既に限界を超えている金融庁審報告書「拒否」
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種への傾斜と薬害の教訓
- 編集長コラム「飛耳長目」~情報を取捨できる意義
- 編集長コラム「飛耳長目」~指定弁護士控訴への疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~「終わりの始まり」の年を送って
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種と情報公開への危機感
- 編集長コラム「飛耳長目」~令状発付裁判官の人権感覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定が教えている深刻な司法機能不全
- 編集長コラム「飛耳長目」~トランプ政権の暴走と日本の現実から捉えるべきこと
- 編集長コラム「飛耳長目」~緊急事態宣言下の五輪開催が示すこの国の病
- 編集長コラム「飛耳長目」~「市民感覚との乖離」批判の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~ゲーリングの言葉と「コロナ禍」日本
- 編集長コラム「飛耳長目」~「期待権」を持ち出した民主「法曹養成制度改革緊急提言」の印象
- 編集長コラム「飛耳長目」~市民再判断の事態からみえる裁判員制度の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~刑事司法改革の「引き換え条件」
- 編集長コラム「飛耳長目」~冤罪防止と裁判員制度の危うい期待感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「全能感」という宿痾
- 編集長コラム「飛耳長目」~ウクライナ支援と憲法9条の立場
- 編集長コラム「飛耳長目」~「高市発言」を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~選挙結果に反映しなかった「危機」のリアリティ
- 編集長コラム「飛耳長目」~戦争という手段が「常識化」した世界
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定取り消しへの違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「弁護士インフラ論」をめぐる疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~「砂川事件」最高裁長官「漏えい」問題の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判記録廃棄への欠落した意識
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍から学ぶべき日本人の本当の「弱点」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」をめぐる執念と侮り
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判でまかり通る現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「闇バイト」を求める若者たちの「ハードル」
- 編集長コラム「飛耳長目」~重大事件関与で問われる裁判員制度の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹人口増員論議のステージ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「獄死」という幕引きへの「意思」