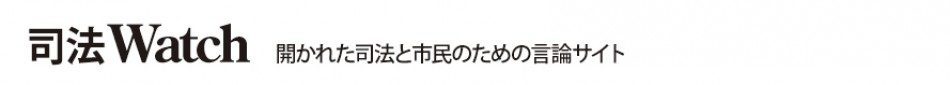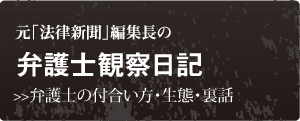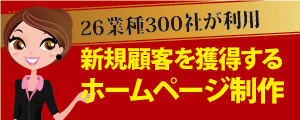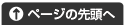司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
「日本人ファースト」という言葉が、参院選を前に一部政党の掲げていることとも絡んで、にわかに注目され、関心を高めている。そして、それは見方によっては、既に分断の様相を呈しているといえる。片や自国の国民の利益を当然に優先されるべき、という発想、片やこの言葉の先に予想される排外主義への危機感の隔絶である。
一見して、既にこの隔絶は埋め難いようにみえる。この言葉を掲げることを前者の立場の国民は、どの国にも見られる「健全な」ナショナリズムの範疇ととらえ、その立場に立たない、立てない日本の現実に強い不満を示す。それは、彼らからすれば当然に、これに「排外主義」を被せ、懸念する国民やメディアへの強い批判にもなる。
一方、後者の立場からは、自国民の利益を優先する、自国民中心のナショナリズムが、「排他的」に傾倒し、差別に至ることを、およそ歴史的教訓としてとらえる。その自国民の前記不満が大きければ大きいほど、それは歯止めが効かず、差別傾向は煽られる、とみている。
「日本社会に外国人、外国ルーツの人びとを敵視する排外主義が急速に拡大しています」として、この状況に強い危機感を露わにして、7月8日に発表された外国人支援団体など8団体が呼びかけた緊急共同声明では、「日本人ファースト」が既に「へイトスピーチ」として位置付けられている。
しかし、このことそのものが、まさにこの分断した両者の国民の距離感を象徴している。いわばこの国で生きる人間の「当然の」の主張を、「ヘイトスピーチ」と位置付けるような、彼らからみた「不当性」。「排外主義」を懸念する国民もメディアも、直ちにその「不当」な主張の側、もしくはその擁護者とされてしまうからである。
「日本人ファースト」の台頭をめぐり、ひとまず共通理解に立てるところから、アプローチする以外にない。まず、経済の停滞と社会に広がる将来への不安。物価高と賃金の伸び悩み、社会保障制度への懸念など経済的な閉塞感、その一方で労働力不足を背景にした日本政府の外国人受け入れの拡大とその体制の本質的な不備。「外国人優遇」をめぐり、認識も真っ二つに分かれるが、少なくともこれを単純に「フェイク」として片付け、一方を納得させることはできない、背景事情は存在し、また「排他」が、彼ら国民の多くが本来求めている(求めていた)ものでもないはず、ということにもなる。
もちろん「反グローバリズム」という背景も無視できない。国際社会の一員として自国利益の追求だけで繫栄も生存もできない、と一昔前まで多くの人が常識と思っていた価値観が、自国と自分を現実的に救ってくれないし、むしろ犠牲にしているという失望感は、その受け皿となるような政治的主張に当然の助けを求める。いまや世界的な傾向と言われる、その波も当然に共通認識の中に入ってくる。
「日本人ファースト」を支持する側は、それを掲げる勢力の真意とは別に、それを自国の文化や伝統を守ることと同じく、自国民として「当然の」幸福を追求するものであり、「健全なナショナリズム」の枠に収まる、自国民の「権利」と同義のものとして主張し続けるだろう。
一方、国民のそうした思いをよそに、それを掲げる勢力の意図(隠されたものを含み)によって、あるいはその多くの国民の意図と違う形で、結果的にこの国・国民が「排他的ナショナリズム」に傾く可能性は否定できず、その懸念は当然のものとしてあり続けるだろう。
そうなれば、この分断を乗り越える道は、ただ一つだけ。閉塞感を生み出し、国民がこの言葉に活路を見出さざるを得なくしている前提的な事情と、その解消を議論するしかない。今、なぜ「不当に」外国人が優遇されているように思えるのか、なぜ、もっと日本人を大事にしろ、という意識に多くの国民が目覚め出しているのか。
この言葉を「ヘイトスピーチ」として批判すること、あるいは「ヘイトスピーチ」に当たるのかどうかを議論することよりも、いかに迂遠のようにみえても、なぜ、この分断がこの国に生まれ、さらに拡大しようとしているのか、その背景にある、この国の失策を含めた原因を、まず議論すべきである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~重大事件関与で問われる裁判員制度の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度改革の方向から伝わるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~公文書改ざんが罷り通る国のムード
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」「森友問題」から見るこの国の姿
- 編集長コラム「飛耳長目」~果たされない「説明責任」と自覚の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~選択的夫婦別姓が実現しない国の実相
- 編集長コラム「飛耳長目」~「不都合な真実」を引きずる裁判員制度
- 編集長コラム「飛耳長目」~「予備試験」制限という法科大学院「強制」の末路
- 編集長コラム「飛耳長目」~メディアのアンフェアと大衆の立ち位置
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「負の遺産」としての「成功体験」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「砂川事件」最高裁長官「漏えい」問題の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ふさわしさ」という君が代問題の視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヘイトスピーチ」対策口実化の危険
- 編集長コラム「飛耳長目」~「国防軍」が登場する改憲の欲求
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ対策便乗マイナンバー拡大策の胡散臭さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~刑事司法への警戒感不足という現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「資格」の責任、「改革」の責任
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ゴーン被告人逃亡」と「人質司法」の悲観的な展開
- 編集長コラム「飛耳長目」~「司法改革」を求める市民目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~本質的ではない法曹養成「緩和」策の意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度9年から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「闇バイト」を求める若者たちの「ハードル」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「負担軽減」という課題に隠された裁判員制度の課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新潮45」休刊から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「お金持ちしか」論の現実化と「改革」のプライオリティ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「表現の自由」をめぐる覚悟と自覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~注意すべき「利用しやすい」民事司法改革論議
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種を後悔する人々と「同調圧力」社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院撤退原因をめぐる「都合のいい」論調
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験結果からみる政策的「努力」の意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~グロテスクな「予備試験」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~失われた「狭き門」批判のメリット
- 編集長コラム「飛耳長目」~政権と「追認」への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~平和主義と民主主義への危機感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「全能感」という宿痾
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度の「本末転倒」というツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~権力を疑う目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「弔意」が強制される国
- 編集長コラム「飛耳長目」~「知る権利」担保を促す不信感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「国民の理解」登場のご都合主義と軽さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~行き場を失っている裁判官への信頼
- 編集長コラム「飛耳長目」~「仮定の話」という回答拒否論法の悪質さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁判員の声」からみえる制度の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法の支配」を登場させた法曹養成「改革」提案
- 編集長コラム「飛耳長目」~秘密法「体制」下で本当に問われてくること
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定取り消しへの違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「無辜の処罰」を回避する司法との距離
- 編集長コラム「飛耳長目」~「利用されない」ことを恐れる「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「高市発言」を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~憲法9条と「戦争絶対悪」の位置