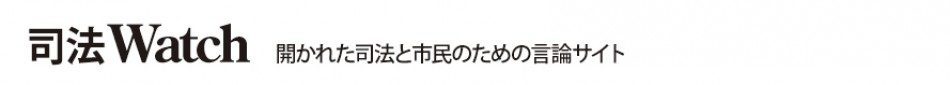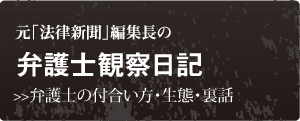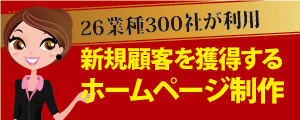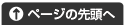司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
石破茂首相の退陣劇は、まさに自民党政権のグロテスクな現実をわれわれに見せつけたものだった。国民的に人気があるとされた石破氏は、政治不信の元凶ともなった裏金問題など「政治とカネ」の問題に、その国民の期待に反して、はじめから「何もできない」姿を見せ続け、選挙でも大敗。挙句の果てに、その裏金問題に関与した旧安倍派議員が、居座ろうとする首相に対する、いわゆる「石破おろし」を唱え出すといった、醜悪な現実まで見せられた。
「『政治とカネ』の問題など政治不信を払拭できていない。私にとって最大の心残りだ。自民党はけじめをつけなければならない」
「多くの方々に配慮し、融和に誠心誠意努めてきたことが、結果として『石破らしさ』を失い、どうしたらよかったのかという思いはある」
退陣の意向を示した会見で、首相が無念をにじませて、ある意味、正直に語ったこの言葉がすべてを物語っているといっていい。
つまりは、「けじめ」をつけさせる、つけよう、と決意して臨んで、仮にトップになっても実現しない。就任後、延々と呻吟し続けて、国民の失望の声を聞きながら、少なくとも「けじめ」については何もできずに去る、あるいは去ることを余儀なくされた首相の姿に、私たちが直視すべきなのは、自民党政治、自民党政権そのもの体質であるはずなのだ。
呻吟する石破首相に、メディアは初めから、繰り返し党内基盤の弱さ、といった注釈を付けてきた。それこそが、石破首相の悲劇のように言う人もいる。どれだけ強い意志をもって「けじめ」に臨もうと、構造的に実現しない現実。皮肉というか、漫画というべきか、あからさまな前記旧安倍派議員の行動を見ても、我々の想像を越える「けじめ」の高いハードルが存在していることをうかがわせる。
参院選の総括で、派閥の裏金問題は「わが党に対する国民の信頼を損なう大きな要因」「自民党に対する不信の底流」という、表向きは厳しい自覚は示されている。しかし、これを決して額面通り、受け止めてはならないという思いにさせるのが、今回の石破首相の退陣という現実なのではないか。
石破氏退陣へ、が報じられて以降、メディアは、次期総裁選候補の話を連日報じている。毎度、国民が直接的に直ちには手を出せない選挙への動向と候補の顔ぶれが報じられているが、前記「けじめ」ということを思えば、もはや暗澹たる気持ちしかしない。この先のどこに、石破首相が果たしたくても果たせなかった「けじめ」を期待できるというのであろう。
有権者向けの耳障りのいい、お決まりの言葉では、「身を切る改革」などということもいわれる。しかし、そういう言葉の一つ一つをわれわれは、常に根本から疑わなければならない。「けじめ」をつけない、つけないで何とかしたい党内の方々と、上手くやっていくのが「長生きの秘訣」だ、ということは、こちらははっきりと分かっているからだ。
ここでも毎度自民党政治・政権に同じことを言わなければならないが、有権者国民は、少なくとも我々が考えてきた以上に、彼らになめられている。有り体に言えば、内向きの前記「長生きの秘訣」を上回る脅威として、国民の反応が実は、いまだ存在していないこと。しかも、二回の選挙で敗北を喫して、国民の声がはっきり伝わり、その痛手を被っても、である。
国民の政治的関心の低さ、メディアの影響が言われ、国民の意識変革と絡めた情報収集、さらなる投票行動の必要性といったことが、判を押したように言われる。その正しさを強調する前に、やはり根本的に私たち国民側が自戒しなければならないのは、やはり政治との緊張関係のなさ、そしてそれを作ってしまっている国民側の厳しい目線、あるいは不信感の決定的な不足であるはずだ。
なんだかんだ言っても相対的に多数の票を集める自民党の現実は、残念ながら彼ら政治家の側に都合のいい解釈や甘えを生ませている。自民党再生を言いながらも、本当に「身を切る」ような「けじめ」がなければ前に進めない、とどれだけの現職議員が、ただいま現在自覚しているだろうか。
「総裁選が『次の選挙の顔』を意識した人気取りと、旧派閥単位の集票合戦に先祖返りするならば、世論とのズレは決定的になる」(9月8日、朝日新聞朝刊1面)
この指摘は、間違っているとはいえない。しかし、人気取りを支えるのも、「世論とのズレ」が「決定的」とまで思わずに駒を進めさせてしまうのも、いうまでもなく、なめられている国民世論であるといわなければならない。彼らが優先する「長生きの秘訣」を通用させなくさせるくらいの、彼らに大きな脅威を与える「不信」とさらなる厳しい目線を、今こそ、国民に求めるべきではないだろうか。「けじめ」はともかく、「次の選挙の顔」を変えてなんとかしようと思っている議員はいないのか。やがて忘れてくれると思っている議員はいないのか――。
石破首相の退陣劇で浮き彫りになっているのは、むしろ私たちの側に必要な強い自戒と自覚ではないだろうか。
- 編集長コラム「飛耳長目」~憲法9条と「戦争絶対悪」の位置
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヘイトスピーチ」対策口実化の危険
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「中核」への疑問という視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~NHK受信料訴訟をめぐる違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~注意すべき「利用しやすい」民事司法改革論議
- 編集長コラム「飛耳長目」~「止めてはならない戦争」という価値観
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験漏洩再発防止策検討と「資質」の断念
- 編集長コラム「飛耳長目」~投票「日当制」提案が映し出す現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員の苦悩からみえる本当の課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~黙秘権の現実と大衆との距離感
- 編集長コラム「飛耳長目」~「強行採決」国会を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ差別と「自己責任」社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~小沢控訴審判決と司法の役割
- 編集長コラム「飛耳長目」~「自粛警察」登場が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「後進国」日本に問われているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~説明責任を無視する政権の危険な自信
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新潮45」休刊から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~元首相暗殺と旧統一教会問題から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制反対「バッシング」の「思い込み」
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判「協働」の無理と危さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~緊急事態宣言下の五輪開催が示すこの国の病
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹養成問題「先送り」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「被害者らしくない」論調と裁判員制度への不安
- 編集長コラム「飛耳長目」~ウクライナ戦争で突き付けられた9条をめぐる「選択」
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹養成に絡めて登場した国会議員の危い司法観
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度からみる「徴兵制」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「フェイクニュース」と判断材料が提供されない社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員への「分かりやすい」喩えの危険度
- 編集長コラム「飛耳長目」~選択的夫婦別姓が実現しない国の実相
- 編集長コラム「飛耳長目」~正気を失わないために
- 編集長コラム「飛耳長目」~「戦争法案」発言で再びみせた安倍タイプ
- 織田信夫
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」再審決定と「修正できない」司法
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍「改憲」姿勢で問われていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判記録廃棄への欠落した意識
- 編集長コラム「飛耳長目」~「総立ち議員」へのこだわるべき「違和感」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「不都合な真実」を引きずる裁判員制度
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹人口増員論議のステージ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁判員の声」からみえる制度の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「敵味方刑法」の影
- 編集長コラム「飛耳長目」~追及できない政治と司法への期待
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「強制閉校」方針が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~秘密法「体制」下で本当に問われてくること
- 編集長コラム「飛耳長目」~「負担軽減」という課題に隠された裁判員制度の課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制、強行採決で見せつけられている現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~岡口罷免判決への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~菅首相「多様性」発言の真意
- Hello world!
- 編集長コラム「飛耳長目」~「稲田発言」への反応と戦争へのハードル
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」法案から見る「世論対策」の軽さ