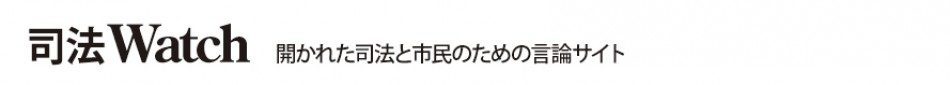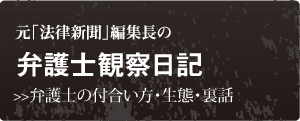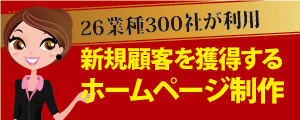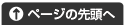司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
インターネット上、とりわけSNS上での誹謗中傷や無責任な言説に対する対策として言われてきた、原則実名主義の必要性をいう論調が以前よりも聞かれなくなりつつある。匿名性そのものが、責任をあいまいにしているという元凶説ともいえるそれが、なぜ、後退しているのだろうか。
その最大の理由は、実名を公開するリスクへの意識の高まりである。個人情報の流出や、いわゆる炎上、さらにいじめ、ストーカーなど現実世界でのトラブルにつながることが、より広く認識され、実名公開への危機意識が高まったことにある。さらには、実名による「なりすまし」の危険性を指摘する声もある。
しかし、これは見方によっては、ネット上での無責任発言、というよりも、発言者が発言への責任をあくまで引き受けるという根本的な発想までも、むしろ不当な批判の回避という目的のために、手放すこと。いわば、その意味では、不当な行為の前に断念せざるを得ない現実を意味する。
それはいま「偏向」という点で、叩かれ出している既存メディア、いわゆる「オールドメディア」との比較でも言われてきた。実名を明らかにし、社名を背負い、責任の所在を明らかにして発信しているメディアと、自由に誰でも発信できて、まさにメディアの偏向性をあぶりだしているかのようなネット情報。
片やフェアに記事を取り上げない「偏向」の懸念、対して匿名性から責任の所在が不明な虚実入り混じった、まさに玉石混交への懸念の間で、情報の取捨を迫られているのが、今の大衆である。
しかし、基本に立ち返れば、実名主義はそう簡単に引っ込めてよいのであろうか。実名主義は責任の所在を明らかにすることで建設的で健全な議論を促す可能性がある。炎上や攻撃の対象化への懸念もいわれるが、実名主義は逆に基本的に批判を受けて立つ姿勢、むしろそこまで確固たる覚悟の上にも発信している、という基本に立つ。いわば、根拠なく、ただ攻撃的に迫る言説と始めから違う立場を表明している。
もちろん、その立脚は、無責任の排除だけでなく、誹謗中傷、名誉棄損、脅迫といった違法行為への一定の抑止効果も期待できる。
一方でデメリットとして、実名発言での身バレによる実生活への影響、個人情報の悪用、発言の委縮といったことがいわれる。しかし、これは本当に実名主義を犠牲にして解決すべきことだろうか。身バレ云々は、むしろ発言者の覚悟の問題であり、むしろ自己抑制がすべて悪いともいえず、委縮を含めて、公正な通報者的発言の保護は、実名を管理者に通告することを条件とする匿名掲示など、別途手段が講じられていい。また個人情報の悪用は、それ自体を問題化すべきで、実名主義が屈服していいこととは思えない。
たとえ現在のように、匿名が認められ、実名主義が全うされなくても、検閲によって、不当な発言は排除される方向にある、という意見もある。しかし、検閲化は、その基準の恣意性という問題を生み出す。何の説明もにく、どこかどういう基準で消されたのか判然としない状況は、また、それこそ公然と言論弾圧がまかりとおることにもなりかねない。管理者にすべての責任を負わす方向にも注意がいる。
自由な発信の場所というネット環境の理解そのものの歪みも指摘しておかなければならない。もとより自由な発信といっても、何でも好きなことを発信していいことではなく、そのために匿名が必要という論法そのものがおかしい。いわゆる単なる「お気持ち」、印象、責任の所在不明な情報をながしてよし、と自由でいいのだろうか。
旧「ツイッター」が登場したとき、これを「つぶやき」と誰かが名付けた。なぜ、これが人に聞かれないくらいに、また、聞かれることを意識してなく発せられた「つぶやき」なのか、という強い違和感を覚えた。思えば、この時からユーザーの勘違い、もしくは誤った方向への傾斜は始まっていたのかもしれない。単なる「お気持ち」はもちろん、内輪話、居酒屋談義でしか通用しないものでも、気楽に、自由に、気にせず、発言していい場が与えられたのだ、と。
「ネットでの発言は、渋谷の交差点で拡声器で話しているのと同じ」と言った人もいる。ネットで発言することそのもののリテラシーとともに、もう一度、発言の責任に目が向けられるべきだ。
- 編集長コラム「飛耳長目」~情報を取捨できる意義
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田首相発言にみる「責任」の空文化
- 編集長コラム「飛耳長目」~量刑をめぐる「裁判員制度無理解」批判の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「オールジャパン」が登場する時
- 編集長コラム「飛耳長目」~「積極的平和主義」の本性
- 編集長コラム「飛耳長目」~「政治的中立」という恐怖
- 編集長コラム「飛耳長目」~行き場を失っている裁判官への信頼
- 編集長コラム「飛耳長目」~自民党派閥「裏金」疑惑事件の教訓
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度改革の方向から伝わるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹の「質・量」確保論の行方
- 編集長コラム「飛耳長目」~死者の美化と「国葬」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「偽ニュース」問題から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹養成を大学運営に委ねたツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~予備試験組司法試験合格率という決定的な現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~最高裁・積極姿勢の「異変」が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「自粛要請」がもたらしている危険な兆候
- 編集長コラム「飛耳長目」~「資格」の責任、「改革」の責任
- 編集長コラム「飛耳長目」~元裁判官の司法改革批判からみえたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~学術会議問題が浮き彫りにしている状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新しい人権」論議の胡散臭さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度が抱えた矛盾と甘え
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験合格者数「死守ライン」到達と今後
- 編集長コラム「飛耳長目」~自民改憲草案「免罪符」論が伝える本性
- 編集長コラム「飛耳長目」~「STAP騒動」にみる「権威」の中の油断と軽視
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の体質を許してきたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」一審裁判官の告白が投げかけた重い課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~「仮定の話」という回答拒否論法の悪質さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~マスメディア批判と「両論併記」の努力
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁判員バッジ」が象徴する制度の無神経
- 編集長コラム「飛耳長目」~黙秘権の現実と大衆との距離感
- 編集長コラム「飛耳長目」~新法曹養成制度維持にとっての苦しい「活路」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」再審無罪が断罪した司法の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ゴーン被告人逃亡」と「人質司法」の悲観的な展開
- 編集長コラム「飛耳長目」~東京五輪開催「ありき」論で試されている感性
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍首相の「リーダーシップ」と「独裁」
- 編集長コラム「飛耳長目」~本当の危機感が伝わってこない「改革」路線維持
- 編集長コラム「飛耳長目」~「保釈率」をめぐる不安要素
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験合格1500人と弁護士増への認識
- 編集長コラム「飛耳長目」~「お金持ちしか」論の現実化と「改革」のプライオリティ
- 編集長コラム「飛耳長目」~武器輸出拡大とわが国が守ってきた「価値」
- 編集長コラム「飛耳長目」~伊方原発差し止め高裁判断と福島事故の教訓
- 編集長コラム「飛耳長目」~「逆張り」論調の価値と健全さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「体罰」容認の経験と空気
- 編集長コラム「飛耳長目」~多様性への不誠実さという視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍から学ぶべき日本人の本当の「弱点」
- 編集長コラム「飛耳長目」~自衛隊による「反戦デモ」敵視問題と想像力
- 編集長コラム「飛耳長目」~「決められない」批判の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~苦しい裁判員制度世論調査結果
- 編集長コラム「飛耳長目」~本質的ではない法曹養成「緩和」策の意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~問われる「職務全う」論への目線