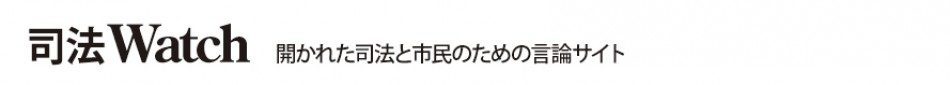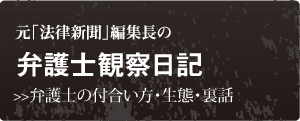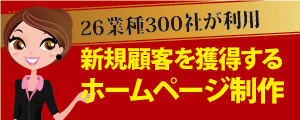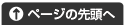司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
問題になっている取り調べ時の暴言などの検察官の不祥事が何に起因しているについて、元検察官の郷原信郎弁護士が新聞紙上で、個々人の問題というより、それは検察組織全体の病理としての「ゆがんだ全能感」であると喝破したことが、話題になっている(朝日新聞1月28日付朝刊オピニオン面「耕論」)。
起訴された事件の有罪率99%、犯罪率の低さや検挙率の高さ、治安の良さから来る国民の検察組織への信頼、造船疑獄での指揮権発動批判以降の「検察の正義」の神聖不可侵化や、ロッキード事件での「総理の犯罪」摘発で刻まれた巨悪対決の特捜の存在感といった歴史的な経緯――。
郷原弁護士が指摘するわが国検察を取り巻いてきた現実は、まさにその病理につながる事情として、極めて説得力のあるものにとれた。この事情のもとで、日本の検察は、「全能感」による誤った正義感を育んでしまったのか、と。
しかしながら、一旦目を離してみると、実は検察組織に限らず、今、日本で、いや世界といっていいかもしれない、現代人間社会で起きている、問題事象の多くが、人間の「全能感」に紐付けられるのではないか、ということに気付かされる。
日本にあっては、政権や政治家、官僚組織の腐敗、不祥事と隠ぺい体質、企業などをはじめあらゆる組織や業界で問題とされているパワハラやセクハラ。前記のような、育まれてきた経緯・事情は異なれど、すべてはそこにいる当事者たちの「全能感」に起因しているようにとれてしまう。そここそ、海を越えて見ても、他国への侵略を命じた、「皇帝」のごとき御仁や、就任早々「力による平和」を掲げ、前政権からの大転換を図る大統領令を連発している御仁にしても、まさにこの言葉の主と括れてしまいそうではないか。
言ってみれば、「全能感」とは、ある条件や地位を得た人間が陥る、自分は「許される」「許された」と思い込んでしまう、いわば大いなる勘違いである。その時、他者からは見えている不当性を、ご本人は見えていないという盲目性がこれを支えている。
ある地位にいる人間が犯す舌禍事件やパワハラにしても、仮に発覚し、社会の眼にさらされれば、どういうことになるか、経験豊富なはずの当事者が、信じられないほど想定できていなかったりする。明るみになった時のことを恐れて、手控える人間の資質は本物として評価できるか、という議論はあるにしても、地位によって盲目になる人間の資質はもっと問われていいように思う。
ただ、それは見方によっては、問題発覚後、訂正や謝罪会見をして、なんとか凌ごうとする、内心はレベルの「全能感」の主といえるのかもしれない。取り繕うともせず、すべて批判も跳ね返せる、あるいはもみ消せる立場にいる、という「全能感」の主もいるとお見受けする。重度といっていいかもしれない。
この言葉を考えるとき、成功体験ということもキーワードといえそうである。つまりは、その地位についてからの、もしくはそうした地位を獲得した過去の第三者の成功実績が、「全能感」を定着化させ、確信させる。現実的に社会が許容したか、され得るかを脇においた実績は、当事者にとっての「やり得」感、逆に言うとそれを行使しないことの損の感情を増大化させるのかもしれない。
話を検察の「全能感」に話を戻すと、記事のなかで、郷原弁護士は、検察が本来あるべき「正義」に立ち返るために必要なものとして、法相の指揮権に注目している。彼は、こう記事を結んでいる。
「議院内閣制の下、民主的正統性を持つ法相が検察の『全能感』にメスを入れ、説明責任を果たさせる。政治的動機の不当な指揮権行使は、諮問機関の設置などで防ぎ、最終的には主権者の国民が選挙を通じて審判を下す。それが民主国家のあり方ではないでしょうか」
法相の指揮権によって、「全能感」の上に乗っかった勘違いを目覚めさせる、あるいはそれが現実的に通用しない手段をとることへの提案だが、その法相がそれこそ「全能感」の主として指揮権を行使することへの歯止めも忘れていない。
だが、結局、ここで重要とされているものは、国民の眼と意識である。審判の現実的な脅威が、やはり「全能感」の主を目覚めさせる。これも、検察に限らず、実は前記この社会にはびこる「全能感」に当てはめられそうである。むしろ、「全能感」の成功体験を育ませてしまった責任は、私たちにあるという、私たちの自覚から始めるしか、もはやこの社会の宿痾と言っていいものに立ち向かうことはできないのである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~「無辜の処罰」を回避する司法との距離
- 編集長コラム「飛耳長目」~「安倍政権」支持世論と「提案型」の悪影響
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験合格1500人と弁護士増への認識
- 編集長コラム「飛耳長目」~問題言動の「謝罪」にみる無意味性
- 編集長コラム「飛耳長目」~「逆張り」論調の価値と健全さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員への「分かりやすい」喩えの危険度
- 編集長コラム「飛耳長目」~ジャーナリスト解放と日本の「自己責任」論の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~「別の目的」で動く人たちへの目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~秘密法「体制」下で本当に問われてくること
- 編集長コラム「飛耳長目」~権力による恣意的運用への歯止めという視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~「指揮権発動」騒動の不思議
- 編集長コラム「飛耳長目」~「桜を見る会」前夜祭問題、新展開の本当の深刻さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~検事長定年延長問題で問われていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~菅首相「多様性」発言の真意
- 編集長コラム「飛耳長目」~「緊急事態」下の「優先順位」と弁護士の存在価値
- 編集長コラム「飛耳長目」~「弁護士インフラ論」をめぐる疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~記録を残さない安倍政権の心底
- 編集長コラム「飛耳長目」~緊急事態宣言下の五輪開催が示すこの国の病
- 編集長コラム「飛耳長目」~既に限界を超えている金融庁審報告書「拒否」
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度見直しの発想と無理
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制成立強行での「軽視」が残したもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判「長期化」が浮き彫りにしている制度の無理
- 編集長コラム「飛耳長目」~「電波停止」発言から考えるべき「受け手」側の弱点
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度擁護派に欠落した発想
- 編集長コラム「飛耳長目」~ウクライナ戦争と動員正当化のイメージ
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度9年から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共同」憲法世論調査からみえる状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~防衛力強化・財源論にみる岸田政権の本性
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪組織委会長辞任劇が映し出したもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「政治決断」の政治利用への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法案反対、学者・日弁連共同記者会見で示された認識と現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院在学中受験の効果と意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~伝えられていなかった裁判員制度のツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍日本で懸念すべき、もう一つの「副作用」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「オールジャパン」が登場する時
- 編集長コラム「飛耳長目」~「マスク社会」が映し出しているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判「協働」の無理と危さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種を後悔する人々と「同調圧力」社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度改革の方向から伝わるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「体罰」容認の経験と空気
- 編集長コラム「飛耳長目」~「政治的中立」という恐怖
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ゴーン被告人逃亡」と「人質司法」の悲観的な展開
- 編集長コラム「飛耳長目」~果たされない「説明責任」と自覚の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~「だまされる弁護士」と「だまされる社会」
- 編集長コラム「飛耳長目」~学術会議問題が浮き彫りにしている状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の体質を許してきたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「スパイ防止法」制定という「欲求」
- 編集長コラム「飛耳長目」~投票「日当制」提案が映し出す現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~女性閣僚「在特会」会見の深刻度
- 編集長コラム「飛耳長目」~変わらない「犯人視報道」