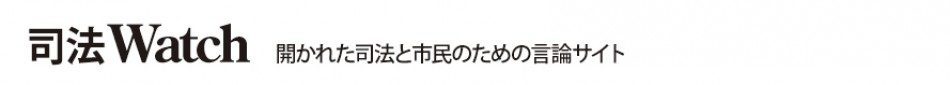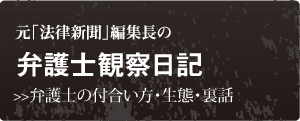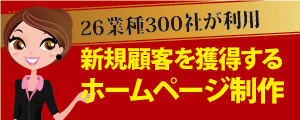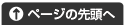司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
「法曹一元」という言葉の意味を、現在、どのくらいの市民が理解しているのだろうか、ということをつい考えてみたくなる。まして、これが弁護士会の長年の悲願であり、かつ「平成の司法改革」にあって、本当にその実現を考えた弁護士たちがいた、という話を聞かされても、そこに現実感といえるものを持つ市民は、おそらくほとんどいないだろう。
そして、いまや弁護士界内においても、そこに現実を見る人はいなくなり、この言葉自体も聞かれなくなりつつある。「弁護士会の長年の悲願」と書いたが、そこに今、仮に「かつての」と前置きしたとしても、それに違和感を持つ弁護士は、おそらく少数派になっているようにすらみえる。
皮肉にも、前記「司法改革」は、弁護士会の悲願達成への大きなターニングポイントになったといえる。弁護士会内「改革」主導層が、この悲願を目標の頂点に掲げ、その道程に、その給源としての意味を加味した弁護士増員や自己改革の必要が唱えられた。激増政策は現実化して、その失敗によって弁護士の経済の環境は大きな打撃を受け、採算性追及への覚悟や精神に大きな変化を生むことになっても、結局、「法曹一元」は実現していない。
そして、実現していないだけでなく、前記したような「改革」が弁護士にもたらした変化こそ、これを実現に導く主体であったはずの弁護士自身から、この「悲願」への関心を奪った観すらある。
弁護士会にとって、この言葉には「官僚司法の打破」というテーゼがぴたっとくっついたものだった。市民に近い法曹である弁護士から、裁判官が選ばれ、その経験が司法に反映されることによって、国民を向いていない官僚裁判官による司法が終了する――。見方によっては、「革命的」とも言いたくなるような、弁護士の強烈な社会的存在感、存在意義を前提とする発想といえるかもしれない。
まさに「革命的」なシナリオも描かれた。
「この年(筆者注2007年)、法科大学院を卒業した『新60期』の司法修習生千余名の修習開始を受け、裁判所や検察庁での実務修習は、受入数が多すぎて機能不全に陥る」「これに代わり豊かな実務修習を提供できる弁護士会が、司法修習を運営」「法科大学院は官僚法曹を養成せず、生の事実に即し、依頼者の立場で法を駆使する法律家を育成する」「合格者増員により、貸与制に移行すれば、修習を強制できなくなるから、国営の司法修習制度は自滅に向かう」「裁判所法42条は、判事補は司法修習生の中から任命すると定めている。だから、司法修習制度がなくなれば、判事補を任命できなくなる。その結果、判事補は絶滅し、判事補の中から判事を任命することができなくなる」「こうして、裁判官のキャリアシステムが消滅し、法曹一元が実現する」(小林正啓弁護士のブログ引用の、法曹一元論者・後藤富士子弁護士の論考から)
「革命」は起きなかった。しかし、そのこともさることながら、注目すべきは、法曹人口増員政策、法科大学院制度、給費制廃止、さらには司法修習廃止までが、すべて前記シナリオには、組み込まれ、法曹一元実現の未来と重ね合わされたことである。結果は、道程に組み込んだはずの政策それぞれが、うまくいかなかった。法曹一元どころではない、それぞれの政策失敗を読み切れていなかった「改革」は、それぞれの「誤算」の影響をまともにくらうことになる。
もっとも当時の多くの弁護士が、前記シナリオを固く信じていたかといえば疑問である。そう簡単にシナリオに沿って、弁護士・会がイニシアティブを握る司法が、やすやすと実現するという甘い見通しを立てていたとは思えない。その意味では、当時「革命前夜」的なムードが、弁護士界を支配していたとみるのは、少なくとも見てきた印象とはかなり違うと言わざるを得ない(「激増政策の中で消えた『法曹一元』」 )。
ただ、むしろ問題は、こうしたシナリオの描き方そのものが、前記「誤算」を生むことになる「改革」の諸政策に対して、本来反対勢力になってもおかしくなかった弁護士界内世論を、「改革」推進側に取り込むための「方便」に使われていたととれることである(「弁護士激増と競争への想定と『覚悟』」)。
「改革」と「法曹一元」論の後退を語るならば、実は言及すべきもっと肝心なことがある。弁護士から裁判官が選ばれる制度、つまり現在の裁判官制度よりも、弁護士こそが裁判官に選ばれるべきで、それこそが理想だという社会的コンセンサスは醸成されたのか、いや、醸成されつつあるのか――。
「法曹一元」制度は、弁護士の、裁判官に対する資質的な優越性を前提とし、まさにその点において、国民に信頼される存在でなければならない。弁護士を経なければ、生の社会的な現実を理解し、当事者の立場を正しく理解した司法判断は下せないという、絶対的な国民の認識を背景にする必要がある。
「平成の司法改革」は、一見この部分の期待感を、裁判員制度が被る形になったようにもとれるが、はっきりいえることは、この面でも「改革」の結果は、弁護士に対する国民の印象を、皮肉にもおよそ「法曹一元」の描いた理想から遠ざけるものになった、としか思えない。
なぜか「改革」の結果と、国民の信頼の情勢と、「法曹一元」との距離もまた、いまや語られなくなっているのが現実なのである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~「高市発言」を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「順法精神」利用への危機意識
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ファクトチェック」の正統性への疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~「STAP騒動」にみる「権威」の中の油断と軽視
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田政権がみせた国民との「断絶」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「表現の自由」をめぐる覚悟と自覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~「翼賛」という言葉があてがわれた「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹養成問題「先送り」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「闇バイト」を求める若者たちの「ハードル」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」法案から見る「世論対策」の軽さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「露骨」な秘密保護法案
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定取り消しへの違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~舞鶴女子校生殺害事件から垣間見える捜査当局の思惑と自覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~「保釈率」をめぐる不安要素
- 編集長コラム「飛耳長目」~正気を失わないために
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度が飛び越えようとしているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~再審請求で問われる司法の謙虚さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~南海トラフ地震「注意」喚起と社会実験
- 編集長コラム「飛耳長目」~石破首相の「変節」を生んだもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍首相のなかの「軽視」と「怯え」
- 編集長コラム「飛耳長目」~投票「日当制」提案が映し出す現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験合格1500人と弁護士増への認識
- 編集長コラム「飛耳長目」~支持率に対する政権の姿勢から読み取るべきこと
- 編集長コラム「飛耳長目」~死刑廃止問題と弁護士会内民主主義の狭間
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権下の公文書問題と「隠ぺい」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新しい人権」論議の胡散臭さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~ネット発言の実名主義と責任への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~権力を疑う目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ対策便乗マイナンバー拡大策の胡散臭さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍日本で懸念すべき、もう一つの「副作用」
- 編集長コラム「飛耳長目」~黙秘権の現実と大衆との距離感
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制反対「バッシング」の「思い込み」
- 編集長コラム「飛耳長目」~変わらない「犯人視報道」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ジャニーズ問題」と不問にする社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~「終わりの始まり」の年を送って
- 編集長コラム「飛耳長目」~弁護士「自己改革」の先に待っていたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「自粛要請」がもたらしている危険な兆候
- 編集長コラム「飛耳長目」~市民再判断の事態からみえる裁判員制度の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「負の遺産」としての「成功体験」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「桜を見る会」前夜祭問題、新展開の本当の深刻さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹の「質・量」確保論の行方
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁判員バッジ」が象徴する制度の無神経
- 編集長コラム「飛耳長目」~秘密保護法案強行採決が象徴するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「指揮権発動」騒動の不思議
- 編集長コラム「飛耳長目」~自民・政治資金規正法改正で見えた本性
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院の制度的「無理」という視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~迷走答弁から見える安倍政権の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~結果責任を問わない「改革」推進姿勢の絶望
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田首相発言にみる「責任」の空文化
- 編集長コラム「飛耳長目」~「参入規制」批判のアンフェア