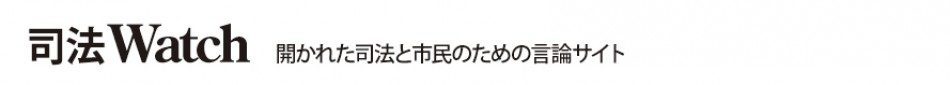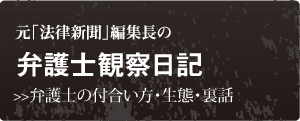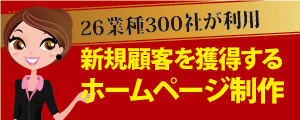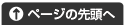司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
私たちの中の「戦争絶対悪」「戦争完全放棄」の意識は、今、どのくらい定着し、その強度はどのくらい保たれているのだろうか。憲法9条が様々な形で取り上げられる度に、その根本にあるべきものの現在という問題にたどり着く。
自衛権、安全保障、国際協力、世界的な常識――。様々な要素が、現実的な課題として、その解釈に加味すべき、あるいは議論すべき事情として、必ず引き合いに出され、9条の解釈とともに、わが国が選択すべき未来の解が、その向こうにあるようにも言われてきた。
しかし、一方で、その時、「戦争絶対悪」「戦争完全放棄」の発想は、本当にフェアに取り上げられたのか。有り体にいえば、本当の意味で、前記事情によって、いわばそこに譲歩が生まれる妥当性が問われてきたのかが、疑わしい。そもそも戦争は、多くの場合、一方、または相互によって、「自衛」を掲げられていることは自明のことだし、安全保障の主張も同様だ。
国際協力や世界的な常識が語られるにしても、そもそも軍隊を保有し、戦争を放棄していない国のスタンスをわが国が範にできないのは当然であり、それが踏まえられているようにもみえない。そのことを踏まえて、別の協力を別の常識で考えるしかできないことを、表明しなければならないはずなのである。
そして、結局、そういう憲法9条の発想を、どこまでも貫けるかどうかは、結局、冒頭の「戦争絶対悪」「戦争完全放棄」に対する、われわれの意識にかかっているのであり、それが試されているということになるのである。
戦後80年の憲法記念日の朝日新聞の社説。タイトルには「この規範を改めて選び取る」とある。
「戦争放棄の現憲法は1928年のパリ不戦条約の精神を継ぎ、その規定は歴史に学んで人類が目指すところでもある。同じ流れにある国連憲章が大国の専横に揺らぐなか、日本も力ずくの世界に舞い戻ろうとしている」
「日本の防衛費は今や国内総生産(GDP)の2%に迫る。すでに十分な巨額だが、2027年度には世界でも五指に入る可能性がある。『備え』に際限がないことは軍拡の世界史に明らかで、妄信すれば専守防衛を掲げながら軍事大国と化してしまう」
「日本はどうか。平和主義を掲げる民主主義国家としてここまで歩んできた。『国民の不断の努力』(第12条)あってこそ保たれる。むき出しの権力にあって、その努力はますます重い意味を持つ」
ここまでの危機意識と国民の「努力」を言う朝日が、根本であるはずの9条が宣明している「戦争絶対悪」「戦争完全放棄」の意識の強度を、国民に問いかけるところが見つけられない。いま、あえてそう言わなければならないのは、ウクライナ戦争でのスタンスにどうしても思いがいくからだ。
朝日を含む日本の大手メディアは、日本の平和主義の立場から、侵略したロシアの「蛮行」を批判するが、一方で領土奪還のために、国民を動員して、まさに「自衛」の名のもとに戦争を継続するウクライナの立場に何も言わない。また、その点、明らかに9条を要する日本の立場とは違うことの注釈を付けずに、他の戦争継続を支援する国と肩を並べて、支援を表明する国に対しても、何も言わない。
つまり、これでは日本は他国の領土侵略に対して、「自衛」の名のもとに、国民を動員した、領土奪還戦争は憲法9条下でも許容する国であることを内外に表明するのと同じ意味を持ってしまう。そう考えたい勢力は、確かに日本の中にもあるだろうが、既に結論を導いているようにみえてしまう。「力ずくの世界」へ舞い戻ることを懸念している立場とは、矛盾しているようにしかみえない。
憲法9条からは、本来、一直線の「即時停戦」が導かれておかしくないが、それに対して、結局大手メディアも、前記したような前記9条の「戦争絶対悪」「戦争完全放棄」を貫かせなくする要素に傾斜し、「やめられない(やめてはならない)戦争」を認めていないか。
そして、一番の問題なのは、そのことによって国民もまた、憲法9条の立場を、多くの議論の頭越しに、そういうものとして既定してしまう、また、事実上、大手メディアがそういう方向にもっていっているということなのである。(「『止めてはならない戦争』という価値観」 「ウクライナ支援と憲法9条の立場」 「ウクライナ停戦への動きと日本国内の論調」)
「正義の戦争よりも不正義の平和の方がいい」
井伏鱒二が代表作「黒い雨」の中で書いたこの言葉こそ、「戦争絶対悪」につながる戦争体験者の偽らざる心情である。領土奪還、自衛という、国家の正義によって、失われてしまう国民の取り返しのつかない命。あくまで、その立場に立つことこそ、「やめてはならない戦争」など存在しない憲法9条の「戦争絶対悪」の思想であり、これを擁している国の国民のあるべき姿であっていい。
- 編集長コラム「飛耳長目」~既に限界を超えている金融庁審報告書「拒否」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「国防軍」が登場する改憲の欲求
- 編集長コラム「飛耳長目」~「判検交流」の疑念とプライド
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新しい人権」論議の胡散臭さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「負の遺産」としての「成功体験」
- 編集長コラム「飛耳長目」~量刑をめぐる「裁判員制度無理解」批判の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院制度見直しの発想と無理
- 編集長コラム「飛耳長目」~正気を失わないために
- 編集長コラム「飛耳長目」~多様性への不誠実さという視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~「積極的平和主義」の本性
- 編集長コラム「飛耳長目」~NHK受信料訴訟をめぐる違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~迷走答弁から見える安倍政権の本質
- 編集長コラム「飛耳長目」~「翼賛」という言葉があてがわれた「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~辺野古訴訟、司法は「民意」をどう扱ったのか
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田政権がみせた国民との「断絶」
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍日本で懸念すべき、もう一つの「副作用」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「無辜の処罰」を回避する司法との距離
- 編集長コラム「飛耳長目」~「露骨」な秘密保護法案
- 編集長コラム「飛耳長目」~受刑者選挙権問題が突き付けるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~歯止めなき国会で成立した歯止めなき法律
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員の苦悩からみえる本当の課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~国会議員「生き残り」ドタバタ劇の危い現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「安倍政権」支持世論と「提案型」の悪影響
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法務大臣」をめぐる慣行の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~すべてを物語る自民憲法改正草案「前文」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁判員の声」からみえる制度の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験受験者「3000人」台時代到来が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「失敗」の認識
- 編集長コラム「飛耳長目」~グロテスクな「予備試験」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~石破首相退陣と「けじめ」の行方
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制反対「バッシング」の「思い込み」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「差別する自由」への危険な兆候
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁く者」のフィロソフィ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「体罰」容認の経験と空気
- 編集長コラム「飛耳長目」~国民の強制動員からみるウクライナ戦争
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「強制閉校」方針が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~最高裁・積極姿勢の「異変」が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「知る権利」担保を促す不信感
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪開催をめぐる言葉に表われたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~指定弁護士控訴への疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定取り消しへの違和感
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験合格者数「死守ライン」到達と今後
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院、「無用」という実績への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~伝えられていなかった裁判員制度のツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種への傾斜と薬害の教訓
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田首相発言にみる「責任」の空文化
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院在学中受験の効果と意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~「フェイクニュース」と判断材料が提供されない社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~追及できない政治と司法への期待
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定が教えている深刻な司法機能不全