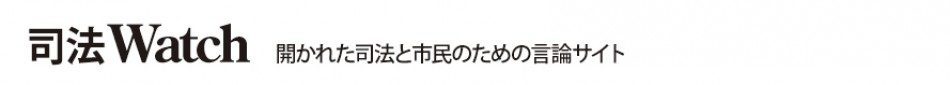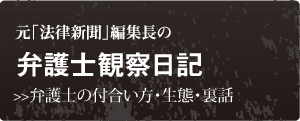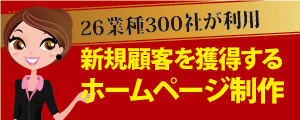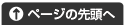司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
市民感覚を裁判に反映させるとか、裁判を分かり易く身近なものにといったことが喧伝された裁判員制度が導入されて、15年以上たったが、肝心の市民や社会の目線は、何がどう変わったのだろうか。ネット空間では、さまざまな刑事裁判に対する、相変わらずの批判的論調が聞かれるが、そのなかで気になる傾向もみられる。
「市民感覚と乖離しているとされたはずなのに」。つまり、「市民感覚」を盾に、逆に「乖離」しているという論調が、むしろ目立っている印象があるのだ。高裁での職業裁判官による判断もさることながら、裁判員制度対象事件以外の量刑も含めて、司法全般に対する、是正されるべき「市民感覚との乖離」が強調されているようになっているととれるのである。
これを、歓迎すべきとする人もいるのかもしれない。まさに市民が自らの感覚と司法との距離をより意識し出した、そのきっかけを作ったのは、裁判員制度の導入なのだと、手放しに礼賛する人も制度推進派の人間もいるかもしれない。
しかし、この「市民感覚との乖離」が振りかざされる司法への批判は、一方で極めて危ういものをはらむことを我々は知らなければならない。なぜならば、司法判断は、常に多数の「市民感覚」を反映することが、その目的ではないからである。この社会の多数派が持っている「市民感覚」とそぐわない結論でも、時に証拠と法に基づいて判断を下さなければならない、むしろそこで超然とした姿勢をとらなければならないのが司法なのである。
これは、裁判員制度導入の功罪と言えるものなのかもしれない。大マスコミを含む制度推進派は、この「市民感覚の反映」を裁判員制度のメリット、あるいは導入の意義として強調し、礼賛した。しかし、制度導入ありきの流れのなかで、その中身は刑事裁判の理解を前提にするには、結果的に偏ったものになっていたといわなければならない。
例えば、「市民感覚」の反映は、社会にある感情やお気持ち、気分が裁判に常に反映した結論を導き出すことを意味しない。あくまで法と証拠に基づいた結論でなければならないが、制度推進論は、その取捨、区別の必要性と中身の違いを分かり易く説明し、クギをさしたといえるのだろうか。
事実認定において、職業裁判官の、いわば社会常識不足論のようなイメージも広がっている。彼らの常識があまりにおかしいから、市民の感覚がそれを是正すべきだし、それで妥当な事実認定を導き出せるのだ、と。しかし、この論法は、漠然としていて、どこまで現実を語り、どこまで通用する話かも不透明だ。あくまでイメージであり、逆に無作為抽出の市民の常識が常に優位とするのは、制度としてのあくまで仮定、イメージのようにも取れる。
しかも、裁判員制度においては、市民は量刑にも参加する。量刑は、刑罰の本質や目的を踏まえ、犯行動機や態様など犯罪事情や情状、刑の均衡などを考慮して判断する専門的知見や経験に裏付けられた専門的判断ととらえている人間は、法曹界にも多い。そもそも職業裁判官が適切に説明すれば、素人でも大丈夫といえるものかは疑問なのである。その量刑に対して、「市民感覚との乖離」がどこまで振りかざれていいのか、という市民への理解も議論も注釈なく、制度は導入されている。
程度の問題を強調する意見もある。「乖離」があまりにも存在し、放置できなくなったから、是正しなければならなくなったのだ、と。しかし、この見方もどこまで制度導入の現実と噛み合っているのかは分からない。裁判所は裁判員制度について、途中から完全に、裁判に対する国民の理解増進論になった。制度はそれに寄与するものだというとらえ方で、現行裁判の不当性が「市民感覚」を取り入れなければならない程度に至っている、とは一言も言っていないし、それ認めて反省したわけでもない。
どちらかといえば、裁判が身近になることで、市民の理解が広がり、さらにともに裁く、いわば「共犯」関係によって、裁判批判をかわせるという狙いまで言われている。百歩譲って、裁判への理解を進めたかったという見方ができたとして、その一方で裁判の本質がきちんと理解されないまま、市民が裁判の結論を批判する傾向が強まるのであれば、何の意味があるだろう。
裁判員制度導入を機に、市民がより「市民感覚」に胸を張り、司法との「乖離」をより鋭く指摘するようになっているとすれば、その現実は、諸刃の剣というべきものかもしれない。それは、本当に司法の問題性を浮き彫りにする場合があったとしても、暴走すれば、人民裁判であり、あるいは「乖離」こそが健全となるかもしれない。
「市民感情」に合わないと感じる、司法の結論に接したとき、私たちはそれをなぜ、司法が導かざるを得なかったのかまで一旦立ち止まって考え、「乖離」という言葉で批判すべきか判断する――。そうした冷静さの必要性をわれわれは自覚しなければならないし、また、司法は根気強く社会に向き合い、それを求めていかなくてはならないはずである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」法案から見る「世論対策」の軽さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定が教えている深刻な司法機能不全
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁判員バッジ」が象徴する制度の無神経
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「負の遺産」としての「成功体験」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「よりまし」選挙の落とし穴
- 編集長コラム「飛耳長目」~菅首相「多様性」発言の真意
- 編集長コラム「飛耳長目」~最高裁・積極姿勢の「異変」が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「排除」失速劇が映し出したもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」「森友問題」から見るこの国の姿
- 編集長コラム「飛耳長目」~「体罰」容認の経験と空気
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「適性試験」任意化方針が伝える手詰まり感
- 編集長コラム「飛耳長目」~改革にカギかっこを付けられる弁護士会
- 編集長コラム「飛耳長目」~新法曹養成「多様性」確保の扱われ方への疑問
- 編集長コラム「飛耳長目」~憲法「争点化」をめぐる選挙状況が突き付けているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験合格者数「死守ライン」到達と今後
- 編集長コラム「飛耳長目」~令状発付裁判官の人権感覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~「桜を見る会」前夜祭問題、新展開の本当の深刻さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~元裁判官の司法改革批判からみえたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~説明責任を無視する政権の危険な自信
- 編集長コラム「飛耳長目」~舞鶴女子校生殺害事件から垣間見える捜査当局の思惑と自覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~「不都合な真実」を引きずる裁判員制度
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度をめぐる「市民感覚の反映」と「職業的自覚」
- 編集長コラム「飛耳長目」~再審請求で問われる司法の謙虚さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「予備試験」人気の奇妙な受けとめ方
- 編集長コラム「飛耳長目」~「止めてはならない戦争」という価値観
- 編集長コラム「飛耳長目」~グロテスクな「予備試験」の現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員の苦悩からみえる本当の課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~伝えられていなかった裁判員制度のツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「忖度」の不自然さからみる公文書改ざん事件
- 編集長コラム「飛耳長目」~公文書改ざんが罷り通る国のムード
- 編集長コラム「飛耳長目」~「日本人ファースト」をめぐる分断
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ワンイシュー」批判から見える逆の危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~大日本帝国憲法「復活」請願という状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~石破首相の「変節」を生んだもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~投票「日当制」提案が映し出す現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新潮45」休刊から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権「暴走」を「許す」世論
- 編集長コラム「飛耳長目」~選択的夫婦別姓が実現しない国の実相
- 編集長コラム「飛耳長目」~問われる「職務全う」論への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験漏洩再発防止策検討と「資質」の断念
- 編集長コラム「飛耳長目」~「後進国」日本に問われているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~日本維新の会「綱領」の受けとめ方
- 編集長コラム「飛耳長目」~法学研究者養成の危機が示す「改革」の現在
- 編集長コラム「飛耳長目」~「積極的平和主義」の本性
- 編集長コラム「飛耳長目」~問題言動の「謝罪」にみる無意味性
- 編集長コラム「飛耳長目」~偏狭的ナショナリズムによって失われるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ウクライナ戦争」とわが国で起きていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判「長期」除外の矛盾
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪開催をめぐる言葉に表われたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~防衛力強化・財源論にみる岸田政権の本性