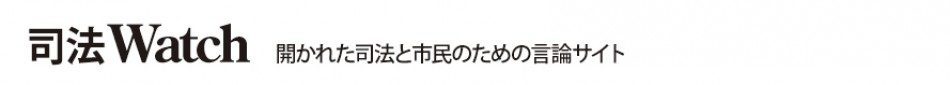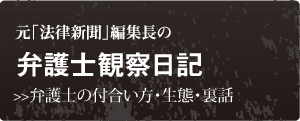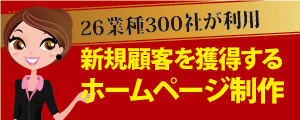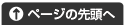司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
「スパイ防止法」制定の必要性が、にわかに取り沙汰されている。日本のいくつかの政党が、制定に前向きな発言をし、先の自民党総裁選でもその必要性が強調されたりしている。米中対立の激化などの影響もあり、経済安全保障の視点が強まっていることも背景にはある。
ただ、同法制定をめぐる動きをみてくると、わが国のいわゆる保守派の中にある、もはや執着と言いたくなる強い制定への「欲求」を見ることになっている。同法制定の議論は、1985年の、日米関係の緊密化や軍事防衛上の包括的防諜体制確立を動機として、最高刑に死刑また無期懲役刑まで含んだ「国家機密法案」にさかのぼる。マスコミ、野党、市民団体の猛反発を受け、審議未了・廃案になった。
たが、「包括的」な法律でなく、スパイ防止を目的とした法律は、既に「分散整備」として、既にこの国で実現している。2013年防衛・外交・テロなど特に秘密が必要なものを「特定秘密」として指定し、漏洩者を処罰する「特定秘密保護法」、2022年に経済面から国家の安全、独立、繁栄を維持・強化することを目的として経済安全保障推進法も成立している。
現在の議論は、これらでは未だ不十分という見方が前提にあるが、保守派の「欲求」ということでいえば、1985年にかなわなかった「包括的」法律を悲願として、「分散整備」の上に、再びそこに持っていこうとするものといえる。「スパイ天国」「諸外国と同水準のものが必要」といった論調も、これに向かって再び息を吹き返すかのように言われ始めている。
彼らの「欲求」が変わらないとともに、これを問題視する側の論調も変わらない、というか、むしろ今もそのまま通用するといっていい。最も基本的に言われ続けているのは、「治安維持法化」への懸念である。処罰対象が拡大し、政府に都合が悪い取材活動を行うジャーナリスト、政府に批判的な市民団体が、「国益を害する」活動としてターゲットになり、スパイ防止法が当局の恣意的な監視・弾圧の強力な「武器」になる危険性である。
前記「欲求」を掲げる側のこれに対する姿勢も、ほとんど変わっていないように見える。あくまで外国勢力のスパイ行為防止とする「あり得ない」論か、一部に極端な思想の人々の排除・監視という目的に一定限度世論の理解が得られるとみているようにとれる論者がいる、という形である。それ以上に、この部分で噛み合った議論の応酬がなされているようにも思えない。
もう一つは、「対米従属」強化の懸念だ。スパイ防止法の大衆から実質的に米国による諜報活動は除外される、その対象は中国、北朝鮮など「敵対国」とされ、事実上それに限られる、という見方である。国際社会で「当然」とするスパイ防止法の、わが国でのこの現実は、独立国として国家主権の問題になるとともに、さらにこの法律が米国の軍事戦略の中で、それに都合がいい形で機能する危険性をはらむ。この根本的な矛盾は、安全保障問題をわが国国民が深く立ち入れないまま、アメリカとの力関係で決まっていくという現実がより国民に浸透する結果となる。
もちろん米国のスパイ活動を対象から外せば、日本が保護すべき情報は米国に事実上筒抜けで、「特定秘密」はすべて米国に提供され、結局、米国が求める情報管理体制が日本国内に構築されるという見方もある。反米右派は、これを問題視するが、保守の主流派は、「同盟維持優先」を軸に、米国との「情報共有」で片付け、対米従属という視点をほとんど無視しているようにもとれる。おそらくこの区別で、国民世論を納得させられるという見立てだろう。
こうみてくると、「スパイ防止法」成立への保守派の「欲求」も、それへの反対論の対立図式もその中身自体も、それほど変わっているようにはとれない。しかし、1985年と大きく変わっているととれることが一つある。それはほかならない世論である。依然、「懸念論」はありながら、対中国、対北朝鮮などへの脅威論によって、その影響力、浸透力が低下し、再び保守派の欲求を跳ね返すだけの力を持っているのかどうか。
特定秘密保護法成立によるスパイ防止関連法の既成事実化と、それによる治安維持法化への懸念減退、日本の技術の海外流出への危機意識の浸透などもあり、かつて「包括的」法廃案へ世論を動かした論調が、どれだけ国民に響くのかもまた見通せなくなっている状況にある。歴史的教訓も通して、スパイ防止法が担ってしまう役割と、「欲求」に引きずられずに必要性の有無を考える冷静な視点をいかに維持するかが問われている。
- 編集長コラム「飛耳長目」~メディアのアンフェアと大衆の立ち位置
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍「改憲」姿勢で問われていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~「体罰」容認の経験と空気
- 編集長コラム「飛耳長目」~原発「推進」復活の動きと求められる視座
- 編集長コラム「飛耳長目」~「総立ち議員」へのこだわるべき「違和感」
- 編集長コラム「飛耳長目」~投票「日当制」提案が映し出す現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~令状発付裁判官の人権感覚
- 編集長コラム「飛耳長目」~派遣法改正という「規制緩和」の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~「資格」の責任、「改革」の責任
- 編集長コラム「飛耳長目」~「翼賛」という言葉があてがわれた「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「知る権利」担保を促す不信感
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験受験者「3000人」台時代到来が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験合格者数「死守ライン」到達と今後
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田首相発言にみる「責任」の空文化
- 編集長コラム「飛耳長目」~国民を「なめている」政治
- 編集長コラム「飛耳長目」~自衛隊による「反戦デモ」敵視問題と想像力
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の「負の遺産」としての「成功体験」
- 編集長コラム「飛耳長目」~岡口罷免判決への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「獄死」という幕引きへの「意思」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田」再審開始決定が教えている深刻な司法機能不全
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判でまかり通る現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判、「加工証拠」が示す無理と矛盾
- 編集長コラム「飛耳長目」~「停戦」を前提としない「支援」の見え方
- 編集長コラム「飛耳長目」~メディアの扱いに差が生まれた2つのデモ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「司法改革20年」、朝日「社説」から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪開催をめぐる言葉に表われたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~新しい刑事司法への思惑と目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「偽ニュース」問題から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~問われる「職務全う」論への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「電波停止」発言から考えるべき「受け手」側の弱点
- 編集長コラム「飛耳長目」~取り調べ「全過程可視化」への抵抗を許すもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍日本で懸念すべき、もう一つの「副作用」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共同」憲法世論調査からみえる状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~「人質司法」への認識
- 編集長コラム「飛耳長目」~「難民」に対する本当の目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「負担軽減」という課題に隠された裁判員制度の課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~すべてを物語る自民憲法改正草案「前文」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ゴーン被告人逃亡」と「人質司法」の悲観的な展開
- 編集長コラム「飛耳長目」~「マスク社会」が映し出しているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~公文書改ざんが罷り通る国のムード
- 編集長コラム「飛耳長目」~「よりまし」選挙の落とし穴
- 編集長コラム「飛耳長目」~伊方原発差し止め高裁判断と福島事故の教訓
- 編集長コラム「飛耳長目」~結果責任を問わない「改革」推進姿勢の絶望
- 編集長コラム「飛耳長目」~「オールジャパン」が登場する時
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法の支配」を登場させた法曹養成「改革」提案
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院、「無用」という実績への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「国民の理解」登場のご都合主義と軽さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「差別する自由」への危険な兆候
- 編集長コラム「飛耳長目」~緊急事態宣言下の五輪開催が示すこの国の病
- 編集長コラム「飛耳長目」~「止めてはならない戦争」という価値観