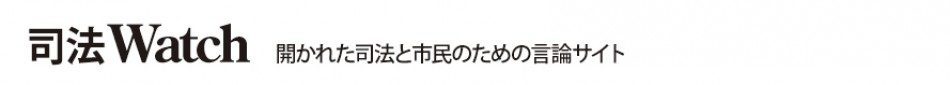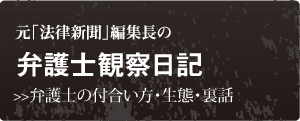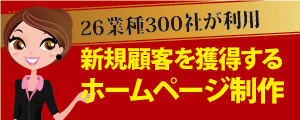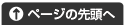司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
わが国での選択的夫婦別姓導入をめぐる状況から、私たちが注目すべき現実は何か、と問われれば、とりもなおさずそれは、何ゆえにここまでわが国でこれが実現しないのか、ではないだろうか。あくまで婚姻後の姓の選択肢、機会保障であり、かつ、いまや世論調査でも賛成は多数派。それでも導入は実現できていない。既に1996年の選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案答申から、実に30年が経過しようとしている。
法律で夫婦同姓を義務付けている国は、いわゆる「主要国」といわれる国では日本のみとされている。多くの国で夫婦別姓は認められ、同姓の選択は義務付けられていない。もはや、このわが国の現実には、日本の「特異性」という言葉を当てはめてたくなる。
いわゆる保守層から声高に言われ続けてきた代表的な反対論は、「家族の一体感」、また日本の家族観に対し「伝統」という言葉を当てはめる言説である。これは、「家制度」的な価値観、あるいはその残滓とみるしかないだろう。
しかも、反対する保守政治家の持っている観念にとどまらない。導入に賛成が多数となっても、前記保守派の観念を、反対論として通用させている、つまりは賛成が多数であっても、その観念を排斥できない、この社会、大衆の中にある残滓とみるべきだろう。この国の世論は、「薄っすら保守」という見方もあるが、まさに世論で多数でありながら、選択的夫婦別姓を導入できない、わが国の「土壌」を、いまや認めなければならないように思える。
保守的な発想、かつ保守層を支持基盤に持つ高市早苗首相の誕生によって、選択的夫婦別姓導入は、遠のくという見方が、大手メディアで報じられている。いまのところ政権は、選択的夫婦別姓導入に否定的で、旧姓の通称使用拡大・法制化で対応する方向である。
導入賛成派の論拠となってきた、改姓による職業生活上や日常生活上の不便・不利益をいう「実害論」と、個人としての「アイデンティティ論」。通称使用の拡大路線は、うち、より多数派同姓選択の国民に説得力がるとみられてきた「実害論」を崩す試みととれる。いわば、「事足れり」論だ。
通称使用が「実害論」をすべて崩せるわけでなく、国際社会での法的不都合や相続や税制など公的な場面で、今のところ不利益が残るといった見方もあるが、「実害論」が減退すれば、推進派は、「アイデンティティ論」の重点化が余儀なくされる可能性がある。同論の追い風になり得るものがあるとすれば、LGBTQに関する議論の活発化なども背景にした、多様性を受容するような社会風潮、経団連などの経済界からも女性活躍推進、グローバル化の観点から推進する論調が、「国の競争力」という観点からも出されていることだろう。
一方、「実害論」に比べて、「アイデンティティ論」には、根本的な弱点もある。キャリアへの影響や、手続きの煩雑さの問題は、データや具体例を示して主張できるのに対し、個人の内面にかかわる「アイデンティティ論」は、その程度や有無を客観的に証明して伝えるのが困難であることだ。それは、同時に、前記通称使用での「事足れり」論、さらに日本の整った戸籍制度や家族の一体感へのリスクを負ってまでやることか、という論調を突き崩しにくい面がどうしてもある。
ただ、推進派が対峙するのは、積極的に反対しているこの国の保守層だけでなく、彼らに有利な立場を与え、反対派を排斥できず、賛成多数にしてなお、選択的夫婦別姓を実現させなかった、正確に言えば、反対論を圧倒的な賛成論で成り立たなくさせるに至らなかった前記「薄っすら保守」の大衆というべきだ。
現在、賛成にカウントされている多数派大衆も、通称使用を「代替策」とする反対派の論調と「問題解決済み」のアナウンスを、そのまま認識するかもしれない。また、実害緩和の認識が広がれば、女性活躍の障害になるというキャリアへの実害を注視した経済的動機が弱まれば、前記経済界の姿勢にも変化が現れてしまう可能性も考えられる。
どうしても推進派には、悲観的な要素が並んでしまう。推進派はどうやって多数派を賛成につなぎ止められるのだろうか。推進派にできることは、通称使用による「事足れり」論を突き崩す、説得力のある論調を作り出すとともに、「アイデンティティ論」を強化・再構築したロジックで対抗するしかないだろう。
しかし、最も根源的なことは、「薄っすら保守」に位置付けられている大衆が、どれだけ問題の本質を認識し、内なる「家制度」的価値観に気付き、わが国の「土壌」を未来にまでつなげるのかどうか、それを立脚点にまずできるかどうかが試されているということである。
- 編集長コラム「飛耳長目」~「安倍暴走」のブレーキ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「翼賛」という言葉があてがわれた「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~戦争という手段が「常識化」した世界
- 編集長コラム「飛耳長目」~「先導的法科大学院」という期待の形
- 編集長コラム「飛耳長目」~「フェイクニュース」と判断材料が提供されない社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~「新潮45」休刊から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~南海トラフ地震「注意」喚起と社会実験
- 編集長コラム「飛耳長目」~「稲田発言」への反応と戦争へのハードル
- 編集長コラム「飛耳長目」~説明責任を無視する政権の危険な自信
- 編集長コラム「飛耳長目」~「戦争」と「軍事行動」を区別する危うさ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ジャニーズ問題」と不問にする社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~安保法制がもたらそうとしている「分かりやすい」危機
- 編集長コラム「飛耳長目」~国会議員「生き残り」ドタバタ劇の危い現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「敵基地攻撃」能力への傾斜が突き付けているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「証拠捏造」をめぐる最高検の姿勢
- 編集長コラム「飛耳長目」~民事裁判IT化とサポートをめぐる懸念
- 編集長コラム「飛耳長目」~ウクライナ停戦への動きと日本国内の論調
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権が利用し続ける「不安」
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「強制閉校」方針が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~伝えられていなかった裁判員制度のツケ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「反社会的勢力」定義問題が示す危険度
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員「配慮」という目くらまし
- 編集長コラム「飛耳長目」~「政治決断」の政治利用への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員裁判「尊重」最高裁判決が示す状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院「中核」への疑問という視点
- 編集長コラム「飛耳長目」~新法曹養成制度維持にとっての苦しい「活路」
- 編集長コラム「飛耳長目」~原発国賠訴訟最高裁判決が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「共謀罪」をめぐる執念と侮り
- 編集長コラム「飛耳長目」~「関心」の背景にある閉塞状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~「桜を見る会」前夜祭問題、新展開の本当の深刻さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「高市発言」を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~原発「コントロール」発言で問われていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~「判検交流」の疑念とプライド
- 編集長コラム「飛耳長目」~止められない「改革」への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~最高裁・積極姿勢の「異変」が意味するもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~「日本人ファースト」をめぐる分断
- 編集長コラム「飛耳長目」~「総立ち議員」へのこだわるべき「違和感」
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種誘導に専門家が「物語性」を求める現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ危機の中で直視すべき、この国の本当の不幸
- 編集長コラム「飛耳長目」~権力を疑う目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~弁護士による横領という末期的状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~追及できない政治と司法への期待
- 編集長コラム「飛耳長目」~文科省「法科大学院改善プラン」の虚しい「願い」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「緊急事態」下の「優先順位」と弁護士の存在価値
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験漏洩再発防止策検討と「資質」の断念
- 編集長コラム「飛耳長目」~武器輸出拡大とわが国が守ってきた「価値」
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権「暴走」を「許す」世論
- 編集長コラム「飛耳長目」~岸田政権がみせた国民との「断絶」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁く者」のフィロソフィ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「マスク社会」が映し出しているもの