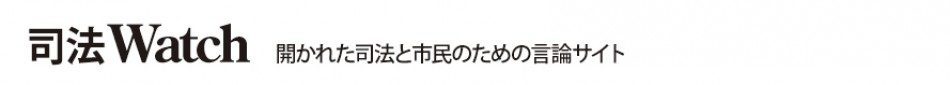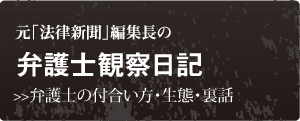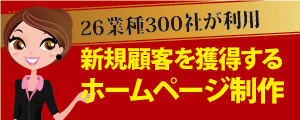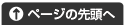司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
イスラエルによるイラン攻撃から始まった戦争状態に、米国が核施設空爆で参戦の報に、いよいよ世界戦争への危機か思われた矢先に、まさに急転直下の停戦合意の発表。権力者たちに、戦争と平和が手玉にとられ、非常に不透明なまま、世界中の市民が脅かされている観がある。
とりわけ、民主主義国家であるアメリカで、「戦争」の選択に対して、もはや民主的な介入がみられない現実に、唖然とする。一体、何が起こり、何が許されているのか。
梅川健・東京大学教授が、6月28日付朝日新聞朝刊オピニオン面「交論」で、この疑問に答えている。
「戦争開始の宣言は議会、その遂行は大統領と権限が分離され、建国の父ハミルトンが強調した通り、王のように専制的には戦争へ進めない。憲法上は、米国の大統領は独断で戦争を始めることができない」
「しかし、現代の米国では別の理論も主張されています。ここ十数年で、大統領は基本的に議会の承認や決議なしに単独で軍事行動ができるという法的、理論的な蓄積がされ、民主党のオバマ政権のころから有力になっています。それが今回のイラン攻撃にもあてはまるという考えかです」
「戦争」と「軍事行動」を区別し、大統領は軍事行動であれば、議会の賛同なしでも行える。地上軍を派遣しない、短期間で終わる、任務が制限された限定的な軍事力の行使で拡大の可能性がない、といった条件を満たせば、それは「戦争」ではない、という。
にわかには信じられないような、極めて危険なご都合主義にとれる。いうまでもなく、短期間で終わるとか、拡大の可能性がない、などという判断がなぜ、できるのか。軍事行動が戦争への引き金になる可能性を、どう否定できるのか。そうなってから、想定外の発展ではもちろん許されない。米国が理屈で許される枠組みを作っても、その影響を受ける諸外国が許せる話ではない。
もちろん、その条件をめぐる判断に、議会という民主的な監視が介入しないことの是非もある。大統領にいかに権限を与えているとはいえ、その判断ミスは米国の場合、即世界に発展する可能性がある。嫌な感じがするのは、便宜的とも言いたくなる、その新たな「軍事行動」の理論を必要とした米国についてである。いうまでもなく、議会を経ずに「軍事行動」に出るメリットを彼らが見出したことである。「戦争」と本来切り離せないはずの「軍事行動」をあえて、無理やりにでも、あるいは便宜的にでも切り離した彼らの真意である。「緊急性」といった、とってつけたような理由では、そのリスクからは到底説明できないはずなのである。
この現実に我々は、どういう目線を向けるべきであろうか。同盟国であり、かつ、軍事的な指揮統制や連携を強化しようとしている国である。単なる「軍事行動」といくら抗弁しようとも、相手国からみれば、「戦争」に踏み出した国の同盟国として捉えられる危険はあることはいうまでもない。
もう一つ嫌な感じがある。もちろん大統領制ではない日本と米国にあって、制度的な前提は違うが、この便宜的な区分の発想を、わが国が「許される」ものとして捉える方向に進む危険である。わが国でも、戦争放棄国として正気の沙汰とは思えない、「敵基地攻撃論」が俎上に上がったりしている。これはあくまで「戦争ではなく、戦争の端緒にはならない」という方便を押し通すならば、「戦争」と「軍事行動」を区別するという米国の論理とさほど変わらなくなる。
国際法上、「軍隊」である自衛隊を、政府が「憲法解釈上、軍隊ではない」と、それこそ便宜的に苦しい判断を示し、多くの国民が一応納得しているように見える日本の現実を考えると、われわれは「戦争」をめぐる便宜的ご都合主義的な二重解釈の矛盾に、もっと敏感になっていくべきように思われる、
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度9年から見えるもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権の体質を許してきたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~メディアとネットが生み出している「分断」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「知名度選挙」という病
- 編集長コラム「飛耳長目」~自覚なき法曹養成見直し案
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員の苦悩からみえる本当の課題
- 編集長コラム「飛耳長目」~歯止めなき国会で成立した歯止めなき法律
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判迅速化をめぐる変わらない懸念材料
- 編集長コラム「飛耳長目」~五輪開催をめぐる言葉に表われたもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~本当の危機感が伝わってこない「改革」路線維持
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験結果からみる政策的「努力」の意味
- 編集長コラム「飛耳長目」~「司法改革」を求める市民目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~国会議員「生き残り」ドタバタ劇の危い現実
- 編集長コラム「飛耳長目」~「反社会的勢力」定義問題が示す危険度
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ヒラメ」が増殖する裁判所体質
- 編集長コラム「飛耳長目」~「裁く」覚悟を伝えていない裁判員制度
- 編集長コラム「飛耳長目」~「仮定の話」という回答拒否論法の悪質さ
- 編集長コラム「飛耳長目」~「敵基地攻撃」能力への傾斜が突き付けているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~コロナ禍から学ぶべき日本人の本当の「弱点」
- 編集長コラム「飛耳長目」~小沢控訴審判決と司法の役割
- 編集長コラム「飛耳長目」~石破首相の「変節」を生んだもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~法科大学院、「無用」という実績への視線
- 編集長コラム「飛耳長目」~安倍政権「暴走」を「許す」世論
- 編集長コラム「飛耳長目」~公文書改ざんが罷り通る国のムード
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」再審有罪立証方針と検察の「メンツ」
- 編集長コラム「飛耳長目」~学術会議問題が浮き彫りにしている状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~誤判・冤罪から問うべき「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「独立性」の価値というテーマ
- 編集長コラム「飛耳長目」~改革にカギかっこを付けられる弁護士会
- 編集長コラム「飛耳長目」~「袴田事件」再審決定と「修正できない」司法
- 編集長コラム「飛耳長目」~「法科大学院」という止まらない列車
- 編集長コラム「飛耳長目」~「捜査中」を言う答弁拒否の正体
- 編集長コラム「飛耳長目」~ハンセン病家族訴訟、「政治決断」への目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「ウクライナ戦争」とわが国で起きていること
- 編集長コラム「飛耳長目」~「だまされる弁護士」と「だまされる社会」
- 編集長コラム「飛耳長目」~9条がもたらした「不戦」への誇り
- 編集長コラム「飛耳長目」~「関心」の背景にある閉塞状況
- 編集長コラム「飛耳長目」~繰り出される「正論」と物分かりのいい国民の問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~「利用されない」ことを恐れる「改革」
- 編集長コラム「飛耳長目」~「差別する自由」への危険な兆候
- 編集長コラム「飛耳長目」~「高市発言」を支えているもの
- 編集長コラム「飛耳長目」~ワクチン接種を後悔する人々と「同調圧力」社会
- 編集長コラム「飛耳長目」~法曹の「質・量」確保論の行方
- 編集長コラム「飛耳長目」~裁判員制度が踏みにじる「民意」
- 編集長コラム「飛耳長目」~政治の責任としての官僚接待問題
- 編集長コラム「飛耳長目」~「弔意」が強制される国
- 編集長コラム「飛耳長目」~「安倍政権」支持世論と「提案型」の悪影響
- 編集長コラム「飛耳長目」~「難民」に対する本当の目線
- 編集長コラム「飛耳長目」~「国防軍」が登場する改憲の欲求
- 編集長コラム「飛耳長目」~司法試験受験者「3000人」台時代到来が意味するもの